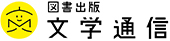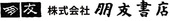目次
第一章 曹丕「典論論文」の文章
一 「典論論文」研究史
二 困難な主題把握
三 政治的意図
四 論旨の矛盾
五 採録時の添削
六 友情物語への改編
第二章 陸機「文賦」の文章
一 「文賦」の評価
二 満腔の自信
三 豊麗な語彙
四 「対偶+比喩」表現
五 うるわしい自然
六 儒道の使いわけ
七 断章取義ふう典故
八 意図的な楽観主義
第三章 沈約「宋書謝霊運伝論」の文章
一 文学ジャンルとしての史論
二 「謝霊運伝論」の評価
三 意図的な名実不一致
四 文学史的記述の価値
五 陸賦・范書との関係
六 硬質の美
七 清弁の行文
第四章 劉勰「文心雕龍序志」の文章
一 駢散の兼行
二 行文のくどさ
三 渋阻なる多し
四 行文の難解さ
五 律儀な叙しかた
六 典故の混乱
七 推敲不足
八 おおいなる実験
第五章 裴子野「雕虫論」の文章
一 「雕虫論」研究史
二 『宋略』の執筆
三 美文への志向
四 地味な語彙
五 生呑活剥の典故
六 「喩虜檄文」の文章
七 文学復古派での位置
第六章 鍾嶸「詩品序」の文章
一 破格な調子
二 希薄な対偶意欲
三 ぞんざいな典故利用
四 杜撰な措辞
五 個性的な表現
六 散在する不具合
七 粗削りの魅力
第七章 蕭統「文選序」の文章
一 「文選序」研究史
二 対偶への配慮
三 論理としての比喩
四 中庸の語彙
五 折衷志向
六 序文代作説
七 温雅な人がら
第八章 蕭綱「与湘東王書」の文章
一 「与湘東王書」の執筆
二 姚思廉の誤解
三 艶詩との関係
四 不用意な対偶
五 文壇の現場報告
六 好悪の情
七 きかんぼう
第九章 徐陵「玉台新詠序」の文章
一 卓抜した修辞
二 才色兼備の麗人
三 謙虚な姿勢
四 幸福な一致
五 麗人編纂説
六 仮構の玉台
第十章 李諤「上隋高帝革文華書」の文章
一 美文による官人登用
二 篤実な対偶研究
三 硬軟語彙の使いわけ
四 実務的文章の改革
五 文学と政治の相関
附篇一 太安万侶「古事記序」の文章
一 絢爛の文
二 非美文ふう表現
三 和習的表現
四 和習おおき報告書
五 過剰な擁護
附篇二 「懐風藻序」の文章
一 積極的な対偶意欲
二 洗練された句法
三 純文学志向
四 感傷性
五 追慕の情
結語 六朝文の評価
一 文章技術からの評価
二 優劣の実際
三 評価基準の構築
四 評価の指標
あとがき
索 引
内容説明
【まえがきより】(抜粋)
文学の良否を論じ優劣を断じるのは、それほど簡単ではない。個人的な感想や好き嫌いを、かたればよいわけではないからだ。もとめられるのは、やはり中正にして公平な評価だろう。そのためには、主観にかたよらぬ、客観的な評価基準が必要になってこよう。そうした客観的な評価基準のひとつとして、文章技術的な基準が有望ではあるまいか。というのは、私が専攻する六朝期の文章作品では、「四六駢儷の体でかけ」という技術的規範が存在するからである。すると、その規範にかなったものが巧妙で、かなわなかったものが拙劣だという評価が可能になってこよう。きちんとした評価をくだすには、前提としてきちんとした基準が必要になるのだが、六朝期はかかる規範が存するため、評価の基準も明確なのである。その意味で六朝の文章作品は、例外的に評価がやりやすい分野だといってよかろう。
では、文章技術的立場から評価をおこなうとすれば、具体的にどのような基準をつくればよいだろうか。たとえば声律をととのえた文章が、そうでないものより高級である。おなじく、対偶、四六、典故、錬字を多用した文章が、そうでないものより洗練されている。さらに対偶では、[対立した内容をならべた]反対のほうが、[相似した字句をつらねた]正対よりもすぐれる。錬字は多用してよいが、口語ふう語彙はつかわぬほうがよい――などがあげられよう。
本書では、そうした基準をやや精細にルール化し、そのうえで当該作はどの点ですぐれ、どの点ですぐれないのかを調査してみた。そのさい、客観性をもたせるため、声律や対偶、四六などの充足ぶりや多寡を数字でしめしてみた。かく修辞の多寡を数字でしめして、それを比較するという試みは、あまりなかったようにおもう。修辞を重視する六朝の文学では、こうした技術方面からの[数字による]評価は重みがあり、また主観のはいりにくいぶん、客観性も担保されやすいだろう。
もっとも、そうした技術方面からの数字だけで、文学作品の評価を決定できるわけではない。創作の時期やジャンルの別、さらには内容の違いなどを無視して、いきなり対偶率や四六率などを比較しても、適切な評価ができるとはかぎらない。そのため章によっては、作品の内実にわけいって、内容と文体の相関をあれこれ論じた議論もあるし、またテキストそれ自体への疑問を呈した場合もある。文章技術方面からだけでは、適切な評価ができないとおもわれた場合は、補助的にそうした方面にも検討をすすめていった。これを要するに、本書では「作品Aはこれこれの内容である」というだけでおわらず、文章技術的な価値判断を基本にしつつ、他の要素も勘案しながら、文学作品としての価値を論じ、その評価をかんがえていったのである。
この書では、六朝の文学批評の文章と、その影響をうけた日本上代の同種の作をとりあげた。具体的にいえば、曹丕「典論論文」や陸機「文賦」、沈約「宋書謝霊運伝論」などからはじまり、附篇の太安万侶「古事記序」と無名氏「懐風藻序」まで、あわせて十二篇である。なぜこれらの作をとりあげたのかといえば、この種の文章は旧時から重要な作として注目をあび、いろいろな評言、つまり作品評価をくわえられてきているからだ。文章技術方面から評価をくだし、その評価の妥当性を測定するには、なるべく[技術方面とことなる]他方面からの評価とも、比較できたほうがよいとかんがえたのである。
その結果、文章技術的な評価と旧時の[他方面からの]評価とは、批評の基準や着眼点がことなるとはいえ、たがいに齟齬するよりも、むしろ相補的な関係になっているようにおもわれた。前者は客観的な基準に依拠し、後者は直感的な判断にかたむいているのだが、長短あいおぎなって、結果的に過不及のない納得できる評価にいたってゆくのが、私にはおもしろく感じられたのだった。
こうした、技術的立場からの評価を旧時のそれと比較しながら、一致点を確認したり、相違する理由をさぐったりすることは、これからの文学研究にも、役だつのではないかとかんがえる。なぜなら、本書では不じゅうぶんなままでおわったが、両方面の評価を吟味しながら、その着眼のしかたや褒貶の判断パターンを比較してゆけば、おのずから旧時の文学評価のメカニズム(いかなる観点から、いかなるやりかたで、いかに評価していたか)が浮きぼりになってくることだろう。そして旧時の評価メカニズムが浮きぼりになれば、評価がなされていない六朝期の作品に対しても、「作品Aは当時どう評価されていたのか」が、[主観や恣意に左右されず]合理的に推定できるようになるとおもわれるからである。