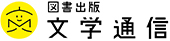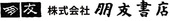内容説明
【序文】より
儒教の伝統は東アジアでは長い歴史をもっている。それは東アジア文明の主要なシンボルの一つである。
ある人々は儒教を、敬慕すべき経験として見なしてきた。それは東方での道徳的公正、家族的結束、社会調和、教育的卓越性、そして政治的結集力への強調であった。他の人々からは、抑圧的で反動的観念形態として、若者たちや女性たちや下層階級の人達を抑圧する役割を果たすものとして、したがって近代化の障害物として見なされた。中国本土では、儒教は二〇世紀の始めごろ、それまでにない強烈な挑戦に直面し、鋭く批判された。その時、中国の知識人たちはすべて、その教えを封建的であり、中国を近代化するにはふさわしくないと拒絶した。その全面的な徹底的滅亡を要求したのであった。この儒教に対する反感は、一九六〇年代の後半、無産階級文化大革命の全盛期に絶頂に達した。年老いた毛沢東主席の激励によって、紅衛兵たちが儒教を、中国の過去の最も有害な残滓として、そして根絶されるべきものとして告発した。しかし、儒教の環境は思いもしない形で変化した。それは、二〇年もたたぬ後のことであった。東亜の“四匹の龍”(ホンコン、シンガポール、台湾、韓国)の経済的奇跡が儒教の性質の再評価をもたらした。この四つの国々はその道徳的価値観からも行動様式からも非常に“儒教”的であったからである。儒教は部分的ではあるとしても、これら“四匹の龍”の経済的成功、科学技術的成功に責任があったであろうか?儒教は現代的なものと本当に矛盾して両立できないのか?いずれにせよ、儒教とは何なのか?宗教は人間生活に究極的な関心をもち、人間存在に最終目標を与える。宗教はまた、ある意味での超越なるものを伝え―その圧倒的実在感、それが畏怖の念を起こさせる。それがあまりにも雄大であるので、他のすべてのものを小さきものとする。
我々が本書において確立しようとしていることは、儒教の伝統はその本質と機能において深く宗教的であるということ、そしていかなる儒教の理解あるいは解釈であっても、単なる人文的、倫理的、社会的、政治的制度では、その本質的核心をとらえそこなうということである。世界の主要な宗教的伝統の中に、儒教の正当な場所を設定する時がきたのである。
【内容目次】
序 文 石 漢 椿
儒教の伝統における宗教的特質 ロッドネイ・L・タイラー
儒教の宗教経典としての四書 石 漢 椿
儒教と中国近代 李 申(訳 日野康一郎)
宗教としての儒教―比較宗教による初歩的検討―
黄 進 興(訳 日野康一郎)
明末中国における十戒の「補儒易仏」性について 葛谷 登
儒教国家としての明―天子の修省を中心に 淺井 紀
儒教と日本神道 奥崎裕司
編集後記 奥崎裕司