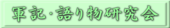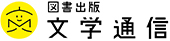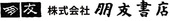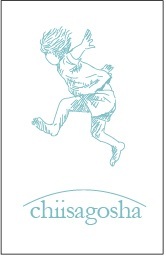創刊号~35
内容説明
雑誌『汲古』バックナンバー
|
|
|
|
第35号 平成11年6月 |
|
|
万葉集訓詁(一) |
久曾神 昇 |
|
伝慶運筆「拾遺現藻和歌集切」考 |
高城弘一 |
|
世阿弥伝書『遊楽習道風見』の本文「流離梟」再考 |
重田みち |
|
「開成所刊行」の朱印と開成所刊行物 |
櫻井豪人 |
|
『漢書』芸文志所載『杜林蒼頡訓纂』『杜林蒼頡故』について |
福田哲之 |
|
王陽明作「九声四気」の歌法資料について |
鶴成久章 |
|
九大本『陽明先生詩録』小考 |
水野 實 |
|
鈔本『謇齋瑣綴録』の補筆について |
川越泰博 |
|
太田辰夫先生を偲ぶ |
飯田吉朗 |
|
『朱子語類』巻二訳注(三) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第34号 平成11年1月 |
|
|
仮名古筆(二五) |
久曾神 昇 |
|
竹柏園旧蔵の「松花和歌集」巻三断簡について 付、伝兼空筆下田屋切の一葉 |
福田秀一 |
|
列帖装について |
櫛笥節男 |
|
「列帖装」の実体と名称 |
八嶌正治 |
|
東京大学総合図書館所蔵校正本『宋元通鑑』について |
山本 仁 |
|
〔未発表遺稿〕沖縄に関する二つの告白 |
服部四郎 |
|
『朱子語類』巻二訳注(二) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第33号 平成10年6月 |
|
|
仮名古筆(二四) |
久曾神 昇 |
|
鈴鹿本今昔物語集の紙捻りの実年代について |
平林盛得 |
|
沖縄県の角筆文献 |
小林芳規 |
|
新出の「香紙切」から見た『麗花集』再考 |
高城弘一 |
|
九大本『文録』における王守仁の逸詩文 |
水野 実 |
|
明清における『詩源』の受容 |
松尾肇子 |
|
松本にある仁井田陞旧蔵資料 |
井ノ口哲也 |
|
『居官必要』と『実政録』 |
山根幸夫 |
|
『朱子語類』巻二訳注(一) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第32号 平成10年1月 |
|
|
仮名古筆(二三) |
久曾神 昇 |
|
書物の構造について |
森 縣 |
|
『萬葉集目安』の成立と萬葉集訓読について |
小川靖彦 |
|
藤原定家の古典書写 |
依田 泰 |
|
洪咨?「平齋文集」諸本考 |
中嶋 敏 |
|
『楊都御史使虜記』とその遺文について |
川越泰博 |
|
『朱子語類』巻第一訳注(五) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第31号 平成9年7月 |
|
|
仮名古筆(二二) |
久曾神 昇 |
|
新出の「巻子本古今集切」に見られる改竄の事例 |
高城弘一 |
|
覆醤集の異本 |
高橋貞一 |
|
『南海先生文集』と『南海先生集』 |
杉下元明 |
|
『延徳版大学』について |
東 英寿 |
|
鄭金球氏の拙論批判文(『汲古』三〇号掲載)を読んで |
戸崎哲彦 |
|
仁井田・今堀両文庫の漢籍について |
井ノ口哲也 |
|
『朱子語類』巻第一訳注(四) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第30号 平成8年11月 |
|
|
記念号 |
|
|
仮名古筆(二一) |
久曾神 昇 |
|
古書随筆 |
福井 保 |
|
書陵部蔵本に於ける鳥の子全紙について |
八嶌正治 |
|
綴葉装本及び粘葉装本の書写と装訂の前後関係について |
櫛笥節男 |
|
関西大学図書館所蔵手鑑『二十四孝』について |
橋本草子 |
|
琉球版『論語集註』について |
榮野川敦 |
|
『太平広記』と宋代仏教史籍 |
竺沙雅章 |
|
柳宗元を祭祀・紀念する廊宇は何時始めて愚渓の北に建てられたか |
鄭金球 |
|
厳修の『東遊日記』 |
山根 幸夫 |
|
『朱子語類』巻第一訳注(三) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第29号 平成8年7月 |
|
|
仮名古筆(二〇) |
久曾神 昇 |
|
新出の『夜半の寝覚』末尾欠巻部断簡 |
田中 登 |
|
後小松院宸筆「御裳濯河歌合切」の新資料と装丁に関する新見解 |
高城弘一 |
|
玉木正英蔵書について |
磯前順一 |
|
江馬細香自筆写本管見 |
小林徹行 |
|
『朱子語類』巻第一訳注(二) |
宋明研究会 |
|
古抄本『史記』「秦本紀」の断簡について |
小沢賢二 |
|
|
|
|
第28号 平成7年12月 |
|
|
仮名古筆(一九) |
久曾神 昇 |
|
過済と未済 |
高橋久子 |
|
版本と考訂 |
湯浅幸孫 |
|
『大和本草』の構成と書名 |
杉下元明 |
|
『朱子語類』巻第一訳注(一) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第27号 平成7年6月 |
|
|
仮名古筆(一八) |
久曾神 昇 |
|
「田歌切」資料続考 |
小野恭靖 |
|
豊後国志考 |
後藤均平 |
|
『説文解字』毛氏汲古閣本について |
高橋由利子 |
|
『荘子』所見老?考 |
澤田多喜男 |
|
『?信集』について |
木村 守 |
|
「宋進士題名録と同年小録」追論 |
中嶋 敏 |
|
四庫存目と「四庫全書存目叢書」 |
季羨林・任繼愈・劉俊文 |
|
東川徳治と『典海』編纂の経緯 |
山根幸夫 |
|
朱子語類訳注(一六) |
宋明研究会 |
|
「汲古」第二六号掲載福田哲之氏論文訂正 |
|
|
|
|
|
第26号 平成6年11月 |
|
|
仮名古筆(一七) |
久曾神 昇 |
|
『保元物語』流布本系統写本についての基礎調査稿 |
原水民樹 |
|
福井市立図書館蔵『伊勢源氏十二番女合』について |
中島正二 |
|
類書の発生―『皇覧』の性格をめぐって― |
木島史雄 |
|
宋進士登科題名録と同年小録 |
中嶋 敏 |
|
静嘉堂収蔵『裔夷謀夏録』について |
虞雲国 |
|
『急就篇』皇象本系諸本について |
福田哲之 |
|
朱子語類訳注(一五) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第25号 平成6年6月 |
|
|
汲古書院創立25周年記念号 |
|
|
仮名古筆(一六) |
久曾神 昇 |
|
『有坂本和名集』と『亀井本和名集』 |
鈴木真喜男 |
|
「あがた切」に関する考察 |
別府節子 |
|
『古筆学大成』未載、伝阿仏尼筆「角倉切」の一葉について |
高城弘一 |
|
柳宗元「永州八記」の名称の成立 |
戸崎哲彦 |
|
オーストリア国立図書館所蔵の「坤輿万国全図」について |
青木千枝子 |
|
中国プロテスタント伝道印刷所の金属活字について |
鈴木広光 |
|
和刻本『二十七松堂集』初考 |
林子雄 |
|
朱子語類訳注(一四) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第24号 平成5年11月 |
|
|
玉里文庫本「理学類編」について |
高津 考 |
|
『停雲集』版本攷 |
杉下元明 |
|
『虞初新志』異本考 |
成瀬哲生 |
|
蓬左文庫所蔵『官常政要』について |
渡 昌弘 |
|
朱子語類訳注(一三) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第23号 平成5年7月 |
|
|
古典研究会創立30周年記念号 |
|
|
追悼 松本隆信先生 |
平澤五郎 |
|
仮名古筆(一五)世尊寺定実 |
久曾神昇 |
|
慈円の新出歌 |
田中登 |
|
鷹司家の蔵書印について |
中村一紀 |
|
『反古籠』は森島中良の編著に非ず |
石上敏 |
|
翻刻『小はる治兵衛 中元噂掛鯛』 |
白瀬浩司 |
|
『春秋経伝集解』宋嘉定九年興国軍学刊本と南北朝覆宋刊本について |
増田晴美 |
|
『続修四庫全書提要』と影印本『文字同盟』第三巻「解題」補遺 |
今村与志雄 |
|
新版『文字同盟』を読んで |
顧廷龍 |
|
芸術と目録 |
宇佐見文理 |
|
建文帝の削藩政策と『皇明祖訓』 |
川越泰博 |
|
『両河観風便覧』について |
大沢顕浩 |
|
我が国に現存する「坤輿万国全図」の刊本に関する一考察 |
青木千枝子 |
|
胡文煥編『官途資鑑』について |
山根幸夫 |
|
朱子語類訳注(一二) |
宋明研究会 |
|
景刊『懐徳堂文庫本 史記雕題』について |
戸川芳郎 |
|
|
|
|
第22号 平成4年11月 |
|
|
仮名古筆(一四) |
久曾神昇 |
|
『周南文集』と『周南続稿』 |
杉下元明 |
|
元刊本『周易句解』をめぐって |
村上雅考 |
|
『助語辞』及び江戸時代におけるその流布と影響に関する書誌研究 その二 |
王宝平 |
|
『光丘文庫』所蔵の漢籍(史部)について |
中道邦彦 |
|
東亜同文書院『支那調査報告書』について |
谷光隆 |
|
朱子語類訳注(一一) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第21号 平成4年6月 |
|
|
仮名古筆(一三) |
久曾神昇 |
|
チェンバレン帝大教師時代の資料 |
堀川貴司 |
|
佐藤春夫『車塵集』の原典とその成立(其の2) |
江新鳳 |
|
「覚勝院年譜稿」追補 付正誤表 |
奥田勲 |
|
永州・柳子廟に謁して |
戸崎哲彦 |
|
『助語辞』及び江戸時代におけるその流布と影響に関する書誌研究 |
王宝平 |
|
記島田所見之中国古籍 |
沈燮元 |
|
五代「鎮東軍牆隍記」に引用された「勅」について |
中村裕一 |
|
朱子語類訳注(一〇) |
宋明研究会 |
|
新たにに出現した古活字版『萬病回春』について |
大島新一 |
|
大谷探検隊将来「太玄真一本際妙経道本通微品第一〇」の行方について |
榮新江 |
|
『古本竹書紀年』の出自を遡及する |
小沢賢二 |
|
『静嘉堂文庫宋元版図録』編集余滴 |
増田晴美 |
|
|
|
|
第20号 平成3年12月 |
|
|
仮名古筆(一二) |
久曾神昇 |
|
新勅撰集の切出歌 |
田中登 |
|
曼殊院蔵清輔本古今和歌集管見 |
川上新一郎 |
|
林述齋の蔵書印 |
福井保 |
|
「鶴牧版史記評林」と佐藤一齋 |
齋藤文俊 |
|
三浦梅園『敢語』の「ミせ本」 |
石見輝彦 |
|
抱残守闕 責在後人―島田翰の奇書 |
高橋智 |
|
『江都督納言願文集」総目録附箚記 |
高橋伸幸 |
|
朱子語類訳注(九) |
宋明研究会 |
|
佐藤春夫『車塵集』の原典とその成立(其の1) |
江新鳳 |
|
|
|
|
第19号 平成3年6月 |
|
|
本能寺切千五百番歌合 |
久曾神昇 |
|
玉藻切金葉集の性格 |
田中登 |
|
前漢の時期の二つの楚王の墓の発掘報告について |
上原淳道 |
|
燉煌発見の唐「公式令」残巻の誤字と脱字について |
中村裕一 |
|
漱玉詞の輯本系譜と作品弁別 |
小林徹行 |
|
『大宋中興通俗演義』と『宣和遺事』 |
渡辺宏明 |
|
朱子語類訳注(八) |
宋明研究会 |
|
殷商暦法研究論著目 |
常玉芝 |
|
『和学者総覧』恩顧録付『和学者総覧』正誤表 |
鈴木淳 |
|
古典研究会本『皇明制書』「大誥」対校表 |
山根幸夫 |
|
|
|
|
第18号 平成2年12月 |
|
|
仮名古筆(一一)原型和漢朗詠集 |
久曾神昇 |
|
庭訓往来真名抄依拠資料小考―六月状の場合― |
堀口育男 |
|
塵尾興衰史―宗教思想史的研究 |
王勇 |
|
「関東庁博物館 大谷家出品目録」作成年次について |
中田篤郎 |
|
春秋左氏伝集解及び註疏善本書目、附公羊伝・穀梁伝善本書目(稿) |
財木美樹 |
|
朱子語類訳注(七) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第17号 平成2年6月 |
|
|
仮名古筆(一〇)藤原行経と兄弟 |
久曾神昇 |
|
『仲文章』に関する二・三の考察 |
三木雅博 |
|
『春秋繁露』の偽書説について |
斎木哲郎 |
|
詩語の発想―「人生」表現の場合― |
長谷川滋成 |
|
『鳩巣先生文集』の構成と成立 |
杉下元明 |
|
朱子語類訳注(六) |
宋明研究会 |
|
隋の東都洛陽と『大業雑記』 |
中村裕一 |
|
馬永易『元和録』について |
杉井一臣 |
|
中国近代史資料叢刊「戊戌変法」に見える総理衙門の日本留学生派遣方上奏 |
川村一夫 |
|
『国立国会図書館所蔵・古活字版図録』を愉しむ |
亀井孝 |
|
|
|
|
第16号 平成2年2月 |
|
|
岩倉規夫先生と内閣文庫 |
福井保 |
|
書籍装幀の歴史に於ける折本の位置 |
森縣 |
|
仮名古筆(九)藤原行成 |
久曾神昇 |
|
新出の竹取物語古写断簡 |
田中登 |
|
濁音符「○○」「○-」交用資料としての「梅沢記念館所蔵応安六年本老子」小見 |
西崎亨 |
|
『狂歌新玉集』における書誌的問題 |
鈴木俊幸 |
|
『漢書』の「資料」を求めて |
山田勝芳 |
|
文館詞林第六百十三巻佚文の巻次について |
野沢佳美 |
|
朱子語類訳注(五) |
宋明研究会 |
|
『文献通考』をめぐる明清の評価 |
北川俊昭 |
|
『中国茶書全集』再補遺 |
布目潮? |
|
|
|
|
第15号 平成元年6月 |
|
|
古典研究会創立二五周年・汲古書院創立二〇周年記念号 |
|
|
仮名古筆(八)二十巻本類聚歌合 |
久曾神昇 |
|
新出の病草紙詞書断簡について |
田中登 |
|
『十番の物あらそひ』の諸伝本 |
石川透 |
|
司馬遷に関する一考察 |
楠山修作 |
|
『大唐新語』管見 |
池田温 |
|
宋代小祠廟の賜額について |
金井徳幸 |
|
『大明会典』にみえる明代衛所官の月糧額をめぐって |
川越泰博 |
|
幻の名拓「光緒二年本」の正体―広開土王碑おぼえがき― |
武田幸男 |
|
論語「宰予昼寝」章の古注 |
飯島良子 |
|
朱子語類訳注(四) |
宋明研究会 |
|
李笠翁の肖像画(下) |
伊藤漱平 |
|
訳社の無礼講 |
太田辰夫 |
|
『孝行録』の「明達売子」について―「二十四孝」の問題点― |
金文京 |
|
「?枕」余談―辞書を引くこと― |
戸川芳郎 |
|
張士俊伝補説 |
狩野充徳 |
|
佐伯文庫叢刊『照世盃』解題への反問 |
徳田武 |
|
古活字版の研究と課題 |
弥吉光長 |
|
|
|
|
第14号 昭和63年12月 |
|
|
仮名古筆(七)三色紙 |
久曾神昇 |
|
依田利用の履歴 |
福井保 |
|
「?枕について」補論 |
戸川芳郎 |
|
読「朱子語類読書法」雑記―虚心― |
市川安司 |
|
朱子語類訳注(三) |
宋明研究会 |
|
朱淑真集の二種の版本について―冀勤女士論文の紹介― |
村越喜代美 |
|
飯田龍一・俵元昭著「江戸図の歴史」を読んで |
長澤孝三 |
|
李笠翁の肖像画(上) |
伊藤漱平 |
|
|
|
|
第13号 昭和63年6月 |
|
|
仮名古筆(六)西本願寺蔵国宝三十六人集 |
久曾神昇 |
|
「その香にめづる藤袴」論―歌物語に潜在する漢詩表現― |
佐藤信一 |
|
『倭名類聚抄』所引の『考声切韻』逸文の反切と「慧琳音義」の反切 |
吉池孝一 |
|
『倭名類集抄』所引の『陸詞切韻』 |
中村雅之 |
|
覚印筆『神供法次第 法王様』 |
石神秀美 |
|
朱子語類訳注(二) |
宋明研究会 |
|
佐賀鍋島諸文庫蔵漢籍明版について―遺香堂絵像本忠義水滸伝― |
高山節也 |
|
華清宮とその浴池 |
山内洋一郎 |
|
『中国茶書全集』補遺 |
布目潮? |
|
|
|
|
第12号 昭和62年12月 |
|
|
山岸徳平先生追悼号 |
|
|
故山岸徳平先生略年譜 |
三谷榮一 |
|
弔辞 |
松尾聰 |
|
山岸徳平先生・追悼と回想 |
久曾神昇 |
|
隅田八幡宮蔵古鏡の銘文について |
馬渕和夫 |
|
山岸先生と海恵僧都 |
築島裕 |
|
法華百座聞書抄のことども―付「サルデハ私語」考― |
小林芳規 |
|
趙岐『三輔決録』について |
[弓巾]和順 |
|
「韓本」孟子趙注について |
高橋智 |
|
朱子語類訳注(一)巻一九論語訳注 |
溝口雄三 |
|
柴野栗山原撰『雑字類編』の成立と刊刻について |
竹治貞夫 |
|
仮名古筆(五)万葉集古寫本 |
久曾神昇 |
|
『和漢朗詠集』版本考 |
鈴木健一 |
|
コンピューターであつかえない漢字 |
當山日出夫 |
|
街談巷語 |
澤谷昭次 |
|
|
|
|
第11号 昭和62年6月 |
|
|
仮名古筆(四)十巻本歌合 |
久曾神昇 |
|
「かくひち」と「文のて」 |
小林芳規 |
|
張士俊「沢存堂本広韻」の系譜 |
狩野充徳 |
|
術婆伽説話にみる受容と創造 |
島内景二 |
|
|
|
|
第10号 昭和61年12月 |
|
|
「魯迅添削・呉組?宛増田渉書簡原稿」解説 |
丸山昇 |
|
『魯迅増田渉師弟答問集』跋文補記 |
伊藤漱平 |
|
大連図書館蔵「大谷本」の来歴およびその現状(中) |
伊藤漱平 |
|
仮名古筆(三)古体仮名三種 |
久曾神昇 |
|
幻の「来(き)しかた」―古典文法の一問題― |
小林芳規 |
|
東大寺図書館蔵本華厳祖師伝所載の国語アクセントについて |
西崎亨 |
|
|
|
|
第9号 昭和61年6月 |
|
|
仮名古筆(二)高野切古今集第二種・第三種 |
久曾神昇 |
|
大連図書館蔵「大谷本」の来歴およびその現状(上) |
伊藤漱平 |
|
心経―発心集増補部の撰者についての国語史よりの提言 |
小林芳規 |
|
佐賀鍋島諸文庫蔵漢籍元版について |
高山節也 |
|
林羅山と近世初期名所記の関係について |
鈴木健一 |
|
第8号 昭和60年12月 |
|
|
仮名古筆(一)高野切古今集第一種 |
久曾神昇 |
|
類句和歌集攷 |
武井和人 |
|
江戸派歌人安田躬弦寸描 |
鈴木淳 |
|
北京観書記 その二―双棔書屋読稗小記― |
大塚秀高 |
|
明末の天主教における図像の問題 |
福島仁 |
|
無窮会図書館所蔵、織田覚齋旧蔵、李卓吾評『忠義水滸伝』一百回 |
佐藤錬太郎 |
|
図書館の出納机より |
増田はるみ |
|
|
|
|
第7号 昭和60年7月 |
|
|
古典にみる「本意」思想 |
伊地知鐵男 |
|
異本の興味(七) |
久曾神昇 |
|
林鵞峰の『公羊伝・穀梁伝』刊行をめぐって |
村上雅孝 |
|
羅山点『春秋穀梁伝注疏』―寛永点監本と慶安点閩本― |
戸川芳郎 |
|
『白香山詩集』の覆刻本について |
神鷹徳治 |
|
北京観書記 その一 |
大塚秀高 |
|
|
|
|
第6号 昭和59年11月 |
|
|
草双紙と浮世草子 |
長谷川強 |
|
尾藤二洲の『今世説』書入れについて |
徳田武 |
|
中世における仏典注疏類受容の一形態―『鏡水抄』のこと |
牧野和夫 |
|
異本の興味(六) |
久曾神昇 |
|
大英図書館の善本一、二ほか―(英国訪書報告)― |
林望 |
|
武新立編『明清稀見史籍叙録』 |
山根幸夫 |
|
文語解を読んで |
橋本真 |
|
|
|
|
第5号 昭和59年5月 |
|
|
汲古書院創立十五周年記念 |
|
|
読書家としての松平定信 |
金子和正 |
|
中世文化と仏典書写 |
新井栄蔵 |
|
六地蔵寺法宝蔵訪書記 |
月本雅章 |
|
『武野燭談』の著者 |
竹治貞夫 |
|
宇野明霞の『語辞解』について |
岩見輝彦 |
|
早陽文庫蒐集道中記目録(二) |
長澤規矩也 |
|
異本の興味(五) |
久曾神昇 |
|
一枚の色紙 |
岩倉規夫 |
|
昭和五十八年度新指定国宝、重要文化財概報 |
山本信吉 |
|
|
|
|
第4号 昭和58年11月 |
|
|
早陽文庫蒐集道中記目録(一) |
長澤規矩也 |
|
校書館推治の檢―内訓を中心として― |
藤本幸夫 |
|
異本の興味(四) |
久曾神昇 |
|
『妙修尼詠草』考―阿部遠江守正元と岡田豊前守善章 |
安藤菊二 |
|
慶應義塾図書館魚菜文庫(旧称石泰文庫) |
白石克 |
|
|
|
|
第3号 昭和58年5月 |
|
|
阿部隆一博士追悼号 |
|
|
阿部隆一博士略歴・著作略目録 |
|
|
阿部隆一博士と書誌学 |
榎一雄 |
|
阿部隆一先生を偲ぶ |
岩倉規夫 |
|
阿部隆一先生と斯道文庫 |
松本隆信 |
|
『和刻本儀礼経伝通解』解題補ならびに補続 |
戸川芳郎 |
|
高山寺蔵本東域伝灯目録書誌寸見 |
築島裕 |
|
異本の興味(三) |
久曾神昇 |
|
和刻本漢詩集成所収『蘇東坡絶句』 |
高橋均 |
|
昭和五十七年度の新指定国宝、重要文化財概報 |
山本信吉 |
|
|
|
|
第2号 昭和57年12月 |
|
|
北京南京上海観書記 |
阿部隆一 |
|
異本の興味(二) |
久曾神昇 |
|
書筆の文字と覆製本 |
小林芳規 |
|
不思議な逸文 |
平林盛得 |
|
求版について |
矢島玄亮 |
|
正倉院鳥毛篆書屏風の釈文の誤 |
原田種成 |
|
|
|
|
創刊号 昭和57年5月 |
|
|
徳富氏の蒐集―蘇峰堂だより |
榎一雄 |
|
異本の興味(一) |
久曾神昇 |
|
昼と夜の変り目 |
伊地知鐵男 |
|
訓点資料と古辞書音義 |
築島裕 |
|
本居宣長と『五雑組』 |
竺沙雅章 |
|
唐本の外題換本 |
福井保 |
|
『航海金針』のこと |
長澤孝三 |
|
蒐書とテレパシー |
岩倉規夫 |
|
長澤規矩也先生を思う |
阿部隆一 |