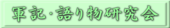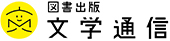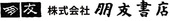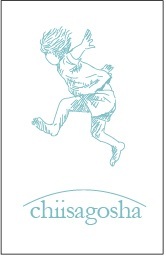36~70
内容説明
雑誌『汲古』バックナンバー
創刊号~35号の目次はこちら
71号~最新号の目次はこちら
|
北宋刊李善注『文選』の版本について |
劉 明 |
|
大倉集古館所藏宋版『韓集擧正』解題訂補 |
佐藤 保 |
|
『全宋文』訂正一則――江万と江万里 |
金 文京 |
|
『覆宋本文選跋』について――袁褧刊本「六家文選」をめぐって―― |
千葉仁美 |
|
朱子語類訳注(一八) |
宮下和大 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第69号 平成28年6月 |
|
|
劉邦と項羽が戦闘した回数について――「合戦する事七十二度」の行方―― |
福田武史 |
|
新出の藤原定家筆「小記録切」(長秋記)断簡を巡って |
髙田智仁 |
|
雲州本「後撰和歌集」について |
福田 孝 |
|
酒田市立光丘文庫所蔵池田玄斎筆『病間雑抄』中の『歌枕名寄』について |
樋口百合子 |
|
国文学研究資料館田藩文庫蔵『十三箇条之記』について――附翻刻―― |
金子 馨 |
|
十市遠忠自歌合捜索願 |
武井和人 |
|
京都国立博物館蔵『榻鴫暁筆』の位置付け――記事の省略の痕跡から―― |
滝澤みか |
|
目録学の観点から見る『春秋繁露』と董仲舒の関係 |
深川真樹 |
|
黄紙詔書再考 |
野口 優 |
|
朱子語類訳注(一七) |
恩田裕正 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第68号 平成27年12月 |
|
|
伝園基氏筆『後嵯峨院御集』断簡 |
久保木秀夫 |
|
今井舎人と鈴木真年―鈴木真年伝の新資料― |
土佐 朋子 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(二十) |
恩田 裕正 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
分野別図書一覧 2005~2015年 |
|
|
第67号 平成27年6月 |
|
|
国立歴史民俗博物館蔵高松宮旧蔵『二十一代集』所収『新拾遺和歌集』をめぐって |
酒井 茂幸 |
|
能『石橋』と『古今集三流抄』 |
中村 健史 |
|
伊藤仁斎「送防州太守水野公序」について |
阿部 光麿 |
|
『太平御覧』所引『玉璽譜』ついて |
田中 一輝 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十九) |
恩田 裕正 |
|
第66号 平成26年12月 |
|
|
内閣文庫蔵『鄒東廓先生詩集』について |
永冨 青地 |
|
名古屋大学文学部図書館蔵『楽府遴奇』について |
平塚 順良 |
|
顔元の佚文一篇 |
林 文孝 |
|
山口素堂の漢詩と邵雍 |
森 博行 |
|
伝冷泉為秀未詳物語断簡考 |
野中 直之 |
|
長澤規矩也先生旧蔵 近世上方子ども絵本 |
木村八重子 |
|
『清話抄』と黒河春村 |
浦野 都志子 |
|
線装はいつ発現したか |
安江 明夫 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十八) |
新田 元規 |
|
第65号 平成26年6月 |
|
|
訓点語研究史における築島裕博士の功績と残された課題 |
小林 芳規 |
|
広開土王碑「多胡碑記念館本」の調査報告 |
武田 幸男 |
|
『萬葉集』(巻十七)の万葉仮名「し」について |
引原 英男 |
|
中山切『古今和歌集』の本文的性格 |
寺田 伝 |
|
承元四年粟田宮歌合について |
日比野 浩信 |
|
『封神演義』第九十九回の問題 |
尾崎 勤 |
|
袋綴じ装の発明と発展 |
安江 明夫 |
|
『改訂増補 漢文学者総覧』書評 |
杉下 元明 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十七) |
新田 元規 |
|
第64号 平成25年12月 |
|
|
田中教忠旧蔵本『懐風藻』について |
土佐 朋子 |
|
李嶠百詠詩題注における和名抄の利用 |
福田 武史 |
|
伝藤原為相筆『土左日記』攷・続貂 |
大島 冴夏 |
|
伝慈円筆烏丸殿切『貫之集』の本文系統 |
北井 佑実子 |
|
書陵部蔵『従二位家隆卿集』残欠本をめぐって |
舟見 一哉 |
|
王紹蘭の『潛夫論箋』補注について |
中村 哲夫 |
|
陳澧『白石詩評』過録批校本・鈔本 |
蕭 振 豪 |
|
冊子の誕生――東洋編 |
安江 明夫 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十六) |
恩田 裕正 |
|
第63号 平成25年6月 |
|
|
『大唐六典』唐令の「開元七年令」説への反論 |
中村裕一 |
|
『類要』中の『通暦』佚文について |
会田大輔 |
|
醍醐寺蔵宋版一切経の雑函に納められた経巻をめぐって |
森岡信幸 |
|
『卜筮元亀』とその周辺 |
宮 紀子 |
|
折本の起源考 |
安江明夫 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十五) |
恩田裕正 |
|
伝冷泉為尹筆四半切後撰和歌集の本文系統 |
立石大樹 |
|
古典語において接頭語とされる「うら―」についての一考察 |
山王丸有紀 |
|
『閑居友』下巻第七話と龐居士説話 |
岩山泰三 |
|
「蟭螟」補注 |
橋本正俊 |
|
第62号 平成24年12月 |
|
|
『懐風藻』未紹介写本三点 |
土佐朋子 |
|
日本古代史料に見える「揚名」の語義――『孝経』の原義との関係―― |
渡辺滋 |
|
史料としての表具 |
髙田智仁 |
|
篠屋宗礀と多福文庫旧蔵本 |
長坂成行 |
|
黒河春村の狂歌――文政時代―― |
浦野都志子 |
|
『漢書藝文志』“暦譜”の意味 |
成家徹郎 |
|
平安後期の入宋僧と北宋新訳仏典 |
大塚紀弘 |
|
陽明学の聖地に残された石刻――「天真精舎勒石」について―― |
鶴成久章 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十四) |
田中有紀 |
|
第61号 平成24年6月 |
|
|
『万葉集』(巻十五)の万葉仮名「之・思・志」と特徴について |
引原英男 |
|
『榻鴫暁筆』の『徒然草』享受 |
稲田利徳 |
|
光悦筆和歌巻に見る書の独自性 |
根本知 |
|
写本『鍾秀集』と『南海先生詩稿』 |
杉下元明 |
|
『漢武帝内伝』『天隠子』両和刻本について――大神貫道と木村蒹葭堂―― |
坂出祥伸 |
|
『菜根譚』佚条五条――明刊諸本について――(附)佚条五条訳注 |
田口一郎 |
|
朱希祖旧蔵『連環記』抄本について |
片倉健博 |
|
蔡大鼎の漢詩文集の諸本について――琉球末期の漢詩文集の刊行を中心に―― |
紺野達也 |
|
南宋越刊『易』、『書』、『周礼』八行本小考 |
李霖 |
|
鄭樵『滎陽家譜前序』について |
唐黎明 |
|
後漢時代における洛陽の文化表象についての考察――「両都賦」解読を中心に |
黄婕 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十三) |
垣内景子 |
|
第60号 平成23年12月 |
|
|
築島裕先生追悼号 |
|
|
築島裕先生略歴 |
|
|
追悼 築島裕先生 |
戸川芳郎 |
|
築島裕博士と聖教調査 |
山本信吉 |
|
築島裕博士を偲ぶ |
小林芳規 |
|
築島先生の訃報に接して |
長澤孝三 |
|
築島裕先生追懐 |
沼本克明 |
|
「律令の古訓点について」に学ぶ |
石上英一 |
|
「せ」と「セ」と――古文書における仮名表記―― |
永村眞 |
|
唐初の「祠令」と大業「祠令」 |
中村裕一 |
|
『万葉集』断簡三種 |
日比野浩信 |
|
『伊勢物語』天理図書館蔵伝為家筆本をめぐって |
久保木秀夫 |
|
「接頭語」と解される「うち―」について |
山王丸有紀 |
|
延慶本平家物語「小松殿大国ニテ善ヲ修シ給事」注解 |
谷口耕一 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十二) |
恩田裕正 |
|
第59号 平成23年6月 |
|
|
築島裕先生追悼 |
|
|
神代紀・神代記により木花開耶姫の本当の夫を復元する |
相見英咲 |
|
伝西行筆『山家心中集』の表記 |
家入博徳 |
|
『山路の露』の新出断簡をめぐって |
中葉芳子 |
|
嵯峨本『伊勢物語』慶長十三年刊第二種本の活字と植字組版について |
鈴木広光 |
|
古活字版調査余録(二)―『後漢書』の刊行年時を考える― |
高木浩明 |
|
古筆切になった春日懐紙 |
田中大士 |
|
黒河春村伝再考―その典拠資料 |
浦野都志子 |
|
六地蔵寺蔵『江都督納言願文集』の濁音符小考 |
西崎亨 |
|
蔡邕『天文志』佚文に見られる渾天儀の構造 |
小沢賢二 |
|
国立公文書館蔵『太平広記』諸版本の所蔵系統 |
塩卓悟 |
|
『一百条』系の漢語鈔本について |
竹越孝 |
|
稿本『語石』について |
池田恭哉 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十一) |
恩田裕正 |
|
第58号 平成22年12月 |
|
|
『對馬國卜部亀卜之次第』の研究 |
辻尾榮市 |
|
『竹取物語』末尾の富士山地名起源説話について |
出雲朝子 |
|
伏見院の書――新出広沢切の紹介を兼ねて―― |
徳植俊之 |
|
『魏鄭公諫録』の成立について |
会田大輔 |
|
北京大学図書館蔵余嘉錫校『弘決外典鈔』について |
河野貴美子 |
|
内閣文庫蔵『東廓鄒先生文集』について |
永冨青地 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十) |
大河内孝史 |
|
上海図書館蔵宋本展と宋代雕版印刷研討会 |
尾崎康 |
|
第57号 平成22年6月 |
|
|
日本のヲコト点の起源と古代韓国語の点吐との関係 |
小林芳規 |
|
康有為『日本書目志』出典考 |
王宝平 |
|
完顔景賢撰・蘇宗仁編『三虞堂書画目』について |
下田章平 |
|
較新の漢字研究 |
志村和久 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(九) |
恩田裕正 |
|
正しからざる引用と批判の「形」 |
平勢隆郎 |
|
春日本万葉集の完全に残る例―付春日懐紙の総数再考― |
田中大士 |
|
伝足利義視筆『徒然草』の古筆切をめぐって |
舟見一哉 |
|
東条琴台旧蔵『君公御蔵目録』小考 |
岩本篤志 |
|
第56号 平成21年12月 |
|
|
新発見隋代陰寿の墓誌 |
韓昇 |
|
陳元靚『博聞録』について |
宮紀子 |
|
天一閣博物館所蔵の三巻本『大象義述』について |
永冨青地 |
|
百二十四回本『水滸伝』について |
氏岡真士 |
|
維経堂蔵板『繡像紅楼夢』について |
森中美樹 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(八) |
恩田裕正 |
|
定家自筆本の制作工程 |
家入博徳 |
|
藤原定家書写『兵範記』紙背文書中にみえる『平家物語』関係文書について |
宮崎肇 |
|
「嵯峨遮那院」について――恵鎮(円観)上人年譜稿訂正―― |
小木曽千代子 |
|
古今和歌集両度聞書の成立――宗祗の自筆原本をめぐって―― |
本位田菊士 |
|
古活字版調査余録――『大和物語』の刊行年時を考える―― |
高木浩明 |
|
近世期京都における経師屋の出版活動 |
万波寿子 |
|
第55号 平成21年6月 |
|
|
日本の経典訓読の一源流――助詞イを手掛りに―― |
小林芳規 |
|
『万葉集』(巻五)における「之・斯・志」について |
引原英男 |
|
古筆切から見た万葉集片仮名訓本――伝解脱上人筆切の場合―― |
田中大士 |
|
伝顕昭筆『伏見院三十首』切の新出断簡 |
日比野浩信 |
|
『狂雲集』――冒頭六首、付加の意味―― |
都田潔 |
|
「伝静覚法親王筆古今集注切」小考 |
徳植俊之 |
|
『六諭衍義大意』の諸本 |
杉下元明 |
|
日蔵『開蒙要訓』断片考 |
張新朋 |
|
邵雍の詩におけるレトリック――「旋風吟二首」について―― |
森博行 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(七) |
高山大毅 |
|
第54号 平成20年12月 |
|
|
宣長門流添景 |
荒木尚 |
|
「隅田川」断簡――「せうこをはゝにまいらすれは」―― |
仁平道明 |
|
『看聞日記』に関する二、三の覚書 |
田代圭一 |
|
『白氏文集』七徳舞の「子在辰」について |
中村裕一 |
|
『中国古代の年中行事』 |
中村裕一 |
|
関西大学図書館内藤文庫蔵『太平広記』について |
塩卓悟 |
|
漢字の通時論的研究 |
志村和久 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(六) |
恩田裕正 |
|
第53号 平成20年6月 |
|
|
日本語訓点表記としての白点・朱点の始原 |
小林芳規 |
|
『土左日記』冒頭部の解釈――清水義秋氏の論考をめぐって―― |
依田泰 |
|
伝西行筆『山家心中集』書誌一考 |
家入博徳 |
|
『翰林五鳳集』の伝本について |
朝倉和 |
|
書陵部蔵宋版一切経の印刷上の一問題 |
山田健三 |
|
『通俗皇明英烈伝』依拠テキストと冠山の訳解態度 |
中村綾 |
|
漢字研究 補遺 |
志村和久 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(五) |
鈴木弘一郎 |
|
増田晴美編著『百万塔陀羅尼の研究 |
尾崎康 |
|
第52号 平成19年12月 |
|
|
米山寅太郎先生・中嶋敏先生追悼号 |
|
|
米山寅太郎先生略歴 |
|
|
米山寅太郎先生を偲んで |
築島裕 |
|
五十余年におよぶ御指導 |
平林盛得 |
|
米山文庫長と私 |
戸川芳郎 |
|
米山寅太郎先生 追想 |
尾崎康 |
|
米山寅太郎先生をしのぶ |
西嶋慎一 |
|
中嶋敏先生略歴 |
|
|
中嶋敏先生著作略目録 |
|
|
お別れのことば |
千葉焈 |
|
中嶋先生の「金屈巵」 |
尾崎康 |
|
彼岸の資治通鑑 |
安野省三 |
|
『金蔵』本の装丁について |
竺沙雅章 |
|
興福寺蔵『経典釋文』及び『講周易疏論家義記』について |
河野貴美子 |
|
「米澤蔵書」からみた江戸期における藩校蔵書の形成 |
岩本篤志 |
|
中国語学者倉石武四郎博士の「蒹葭堂」 |
水田紀久 |
|
『諸儒語要』の王守仁逸言考 |
水野実 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(四) |
大河内孝史 |
|
伝光厳院筆「六条切」の巻頭断簡 |
日比野浩信 |
|
『山家集』と古筆切 |
田中登 |
|
第51号 平成19年6月 |
|
|
米山寅太郎先生追悼 |
|
|
久世切と万葉集抄出本 |
田中大士 |
|
冷泉家時雨亭文庫蔵『仲文集』に見る定家書写本の製作工程 |
家入博徳 |
|
『封神演義』の簡本について |
尾崎勤 |
|
『説文解字』唐写本木部残巻の真偽問題についての何九盈氏論文の紹介 |
白石将人 |
|
二十年先の完訳を望んで――『朱子語類』訳注の刊行開始に当たり |
溝口雄三 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(三) |
恩田裕正 |
|
第50号 平成18年12月 |
|
|
六波羅蜜寺縁起の検討 |
平林盛得 |
|
『遊仙窟』と黒河春村 |
浦野都志子 |
|
『五代集歌枕』の古筆切 |
日比野浩信 |
|
『惟規集』断簡「またしらて」 |
仁平道明 |
|
新出『山路の露』の古写断簡 |
徳武陽子 |
|
中世散佚歌書資料二題 |
池田和臣 |
|
漢字の共時論的研究 |
志村和久 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(二) |
鈴木弘一郎 |
|
第49号 平成18年6月 |
|
|
日本の訓点の一源流 |
小林芳規 |
|
上海図書館蔵『陽明先生与晋渓書』について |
永冨青地 |
|
トレド聖堂参事会図書館蔵『千家詩』(万暦刊本残巻)について |
井上泰山 |
|
元代官府パスパ文字蔵書印管見 |
鵜木基行 |
|
「魏志」韓伝より〈原韓伝〉を復元する |
相見英咲 |
|
新出の浄弁筆「松花和歌集切」小考 |
徳植俊之 |
|
嵯峨本再見―嵯峨本『撰集抄』についての書誌的報告― |
高木浩明 |
|
字解とは何か |
志村和久 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(一) |
恩田裕正 |
|
第48号 平成17年12月 |
|
|
古筆手鑑『翰林帖』 |
久曾神昇 |
|
新出『新撰六帖題和歌』大原切の書誌と本文 |
日比野浩信 |
|
伝為藤筆惟規集断簡 |
仁平道明 |
|
内閣文庫本古今和歌集注(伝冬良作)の古筆切について |
小林強 |
|
文筆問答鈔の版本について |
大石有克 |
|
『禁裡御蔵書目録』の影印本と原本 |
田島公 |
|
『長安志』に引かれた『舊圖經』と大興湯院について |
浜田直也 |
|
朝鮮司訳院の漢学書『象院題語』について |
竹越孝 |
|
『朱子語類』巻九十三訳注(七) |
恩田裕正 |
|
山根幸夫先生追悼文集 |
|
|
第47号 平成17年6月 |
|
|
大江朝綱と継色紙 |
久曾神昇 |
|
春日懐紙祐定目録の解析 |
田中大士 |
|
竹垣城の『麗花集』 |
松本文子 |
|
伝絶海中津作「題太寧寺六首」について |
朝倉和 |
|
小特集 中国日用類書 |
|
|
日用類書にもとづく明代文化研究と今後の展開への期待 |
坂出祥伸 |
|
「中国日用類書集成(汲古書院出版)」の完結に当って |
酒井忠夫 |
|
世界民族図譜としての明代日用類書 |
海野一隆 |
|
日用類書と明清文学―『風月機関』をめぐって― |
小川陽一 |
|
『事林広記』の編者、陳元靚について |
金文京 |
|
中国日用類書解題の再補遺―大谷大学所蔵「明代日用類書」三種など― |
坂出祥伸 |
|
〈中国印刷史〉の研究について |
陳力 |
|
永青文庫所蔵 林羅山自筆訓読『史記』とその周辺 |
加藤陽介 |
|
古抄本『史記』「秦本紀」の断簡について(続) |
小沢賢二 |
|
『朱子語類』巻九十三訳注(六) |
恩田裕正 |
|
第46号 平成16年12月 |
|
|
具平親王集 |
久曾神昇 |
|
惟成集 |
久曾神昇 |
|
源氏物語絵詞二題―絵巻物と古筆切― |
田中登 |
|
二十巻本類聚歌合の新出資料 |
池田和臣 |
|
「ゆるびもてゆく」の「もて」について |
山王丸有紀 |
|
管見『太平記』写本二、三―伝存写本一覧、補遺― |
長坂成行 |
|
漢籍目録編纂における準漢籍の扱いについて |
高橋智 |
|
花関索と楊文広 |
宮紀子 |
|
弋陽腔系散齣集の書誌について |
土屋育子 |
|
『朱子語類』巻九十三訳注(五) |
恩田裕正 |
|
第45号 平成16年6月 |
|
|
寂然自筆唯心房集切 |
久曾神昇 |
|
蜻蛉日記断簡 |
久曾神昇 |
|
『万葉集』中における「万葉仮名」の「之」について |
引原英男 |
|
『平家物語』長門切の一伝存形態 |
日比野浩信 |
|
伝平業兼筆春日切『清慎公(実頼)集』の新出断簡 |
池田和臣 |
|
奈良絵本保元・平治物語について |
原水民樹 |
|
空也と「空也上人の発心求道集」 |
石井義長 |
|
『太平記』書名の由来について |
鎌倉敬三 |
|
唐順之と書傭・胡貿 |
海野洋平 |
|
「怪奇鳥獣図巻」と中国日用類書 |
尾崎勤 |
|
『朱子語類』巻九十三訳注(四) |
恩田裕正 |
|
第44号 平成15年12月 |
|
|
古典研究会創立40周年記念号 |
|
|
寸松庵色紙の筆者 |
久曾神昇 |
|
奏覧本古今集削除五首 |
久曾神昇 |
|
石井義長氏紹介の空也上人『発心求道集』について |
平林盛得 |
|
〈紹介〉宮内庁書陵部恒例展示会「書写と装訂―写す 裁つ 綴じる―」 |
八嶌正治 |
|
冷泉家時雨亭文庫蔵『躬恒集』建長四年本に見る書写意識 |
家入博徳 |
|
古筆手鑑『かりがね帖』と『養老』との浅からぬ関係 |
高城弘一 |
|
二十八巻本『翏翏集』解題 |
山之内正彦 |
|
傳顧歓『道徳真経注疏』所引の『老子注』・『老子疏』 |
栂野茂 |
|
原尊経閣文庫蔵大島維直撰『博士家本史記異字』、『史記考異』の金沢に於ける現状と加賀藩大島贄川の二十一史翻刻の企てについて |
櫻田芳樹 |
|
再び国立国会図書館蔵「天台山記」について |
薄井俊二 |
|
在日清国公使館所蔵の蔵書について |
王宝平 |
|
『朱子語類』巻九十三訳注(三) |
恩田裕正 |
|
第43号 平成15年6月 |
|
|
万葉集訓詁(六) |
久曾神昇 |
|
『とはずがたり』の新出古写断簡 |
田中登 |
|
青洲文庫に就いて |
浦野都志子 |
|
黒水城出土の遼刊本について |
竺沙雅章 |
|
『朱子語類』巻九十三訳注(二) |
恩田裕正 |
|
第42号 平成14年12月 |
|
|
万葉集訓詁(五) |
久曾神昇 |
|
佐藤直方と徒然草 |
島内裕子 |
|
『逍遥遺稿』はいかにして編纂されたか |
杉下元明 |
|
『漢学紀源』の諸本について |
東英寿 |
|
国会図書館所蔵『毛游漫草抄』に就いて |
堀口育男 |
|
郭店竹簡『老子』から見た『老子』の文章 |
澤田多喜男 |
|
『伝習則言』小考 |
水野実 |
|
『中国明朝檔案総匯』について |
甘利弘樹 |
|
『朱子語類』巻九十三訳注(一) |
恩田裕正 |
|
第41号 平成14年6月 |
|
|
国宝西本願寺本三十六人集残存全筆者 |
久曾神昇 |
|
堀直格編『花屋書院略目録』 |
浦野都志子 |
|
整版無刊記本の『長恨歌傳・長恨歌・琵琶行・野馬臺』について |
鎌倉敬三 |
|
宋初の茶書三種(輯逸)について |
水野正明 |
|
国立国会図書館蔵「天台山記」について |
薄井俊二 |
|
台北 国立故宮博物院 主辨「宋元善本図書学術研討会」 |
尾崎康 |
|
『朱子語類』巻二訳注(九) |
宋明研究会 |
|
第40号 平成13年12月 |
|
|
万葉集訓詁(四) |
久曾神 昇 |
|
国宝三十六人集伊勢集等の筆者 |
久曾神 昇 |
|
今撰集の古筆切の紹介 |
小林 強 |
|
宋代単刻本『法華経』について |
竺沙雅章 |
|
大倉集古館所蔵宋版『韓集擧正』について |
佐藤 保 |
|
新出伊地知季安自筆本『漢学紀源』について |
東 英寿 |
|
『昭示奸党録』について |
川越泰博 |
|
姚文棟の日本における古籍蒐集活動について |
陳 捷 |
|
繆咏禾著『明代出版史稿』介紹 |
山根幸夫 |
|
『朱子語類』巻二訳注(八) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第39号 平成13年5月 |
|
|
十巻本歌合の筆者推定 |
久曾神 昇 |
|
伝杉原宗伊筆「正徹詠草切」について |
稲田利徳 |
|
春日懐紙(春日本万葉集)の来歴 |
田中大士 |
|
『歴代残闕日記』について |
浦野都志子 |
|
「寄合書」考究 |
家入博徳 |
|
兼全堂本『警世通言』の成立 |
廣澤裕介 |
|
『朱子語類』巻二訳注(七) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第38号 平成12年12月 |
|
|
部類家集切の筆者――源祐頼 |
久曾神 昇 |
|
「香紙切」複数書者説の先駆 |
松本文子 |
|
冊子東伝説の検討 |
森 縣 |
|
鳥の子紙全紙の大きさと四半本・六半本・八半本の裁断方法 |
櫛笥節男 |
|
北京図書館蔵『大象義述』について |
永冨青地 |
|
黎庶昌の蔵書 |
石田 肇 |
|
『朱子語類』巻二訳注(六) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第37号 平成12年6月 |
|
|
万葉集訓詁(三) |
久曾神 昇 |
|
静嘉堂文庫所蔵の百万塔及び陀羅尼について |
増田晴美 |
|
肖柏奥書本『定家物語』について |
日比野浩信 |
|
『千載佳句』・『和漢朗詠集』所収許渾詩本文をめぐって |
森岡ゆかり |
|
『老子真解』の発兌に際して |
志賀一朗 |
|
東北師範大学所蔵 酔軒 橋川時雄先生遺稿について |
櫻田芳樹 |
|
『儒林外史』研究のこと |
飯田吉郎 |
|
『朱子語類』巻二訳注(五) |
宋明研究会 |
|
|
|
|
第36号 平成11年12月 |
|
|
古典研究会創立36周年・汲古書院創立30周年記念号 |
|
|
万葉集訓詁(二) |
久曾神 昇 |
|
新出伝二条為世筆異本拾遺集巻五(付 巻七断簡)をめぐって |
池田和臣 |
|
幻光庵寂翁の著作について |
川平ひとし |
|
飛鳥池木簡に見られる七世紀の漢文訓読語について |
小林芳規 |
|
慶長勅版『長恨歌琵琶行』『白氏五妃曲』の刊行について |
安野博之 |
|
「北宋・南宋、前宋・後宋」称呼考 |
中嶋 敏 |
|
『陽明先生要書』における王守仁の「遺言」について |
水野 実 |
|
明代の刻書家胡文煥に関する考察 |
王 宝平 |
|
『続脩四庫全書総目提要』と『続脩四庫全書』 |
山根幸夫 |
|
未公開の有坂秀世氏書簡ほか |
服部 旦 |
|
『朱子語類』巻二訳注(四) |
宋明研究会 |
雑誌『汲古』バックナンバー
創刊号~35号の目次はこちら
71号~最新号の目次はこちら
|
第70号 平成28年12月 |
|
|
『和歌類題浪花集』について |
芦田耕一 |
|
冷泉家時雨亭文庫所蔵零本『古今和歌集』の新出断簡 |
寺田 伝 |
|
北宋刊李善注『文選』の版本について |
劉 明 |
|
大倉集古館所藏宋版『韓集擧正』解題訂補 |
佐藤 保 |
|
『全宋文』訂正一則――江万と江万里 |
金 文京 |
|
『覆宋本文選跋』について――袁褧刊本「六家文選」をめぐって―― |
千葉仁美 |
|
朱子語類訳注(一八) |
宮下和大 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第69号 平成28年6月 |
|
|
劉邦と項羽が戦闘した回数について――「合戦する事七十二度」の行方―― |
福田武史 |
|
新出の藤原定家筆「小記録切」(長秋記)断簡を巡って |
髙田智仁 |
|
雲州本「後撰和歌集」について |
福田 孝 |
|
酒田市立光丘文庫所蔵池田玄斎筆『病間雑抄』中の『歌枕名寄』について |
樋口百合子 |
|
国文学研究資料館田藩文庫蔵『十三箇条之記』について――附翻刻―― |
金子 馨 |
|
十市遠忠自歌合捜索願 |
武井和人 |
|
京都国立博物館蔵『榻鴫暁筆』の位置付け――記事の省略の痕跡から―― |
滝澤みか |
|
目録学の観点から見る『春秋繁露』と董仲舒の関係 |
深川真樹 |
|
黄紙詔書再考 |
野口 優 |
|
朱子語類訳注(一七) |
恩田裕正 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第68号 平成27年12月 |
|
|
伝園基氏筆『後嵯峨院御集』断簡 |
久保木秀夫 |
|
今井舎人と鈴木真年―鈴木真年伝の新資料― |
土佐 朋子 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(二十) |
恩田 裕正 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
分野別図書一覧 2005~2015年 |
|
|
第67号 平成27年6月 |
|
|
国立歴史民俗博物館蔵高松宮旧蔵『二十一代集』所収『新拾遺和歌集』をめぐって |
酒井 茂幸 |
|
能『石橋』と『古今集三流抄』 |
中村 健史 |
|
伊藤仁斎「送防州太守水野公序」について |
阿部 光麿 |
|
『太平御覧』所引『玉璽譜』ついて |
田中 一輝 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十九) |
恩田 裕正 |
|
第66号 平成26年12月 |
|
|
内閣文庫蔵『鄒東廓先生詩集』について |
永冨 青地 |
|
名古屋大学文学部図書館蔵『楽府遴奇』について |
平塚 順良 |
|
顔元の佚文一篇 |
林 文孝 |
|
山口素堂の漢詩と邵雍 |
森 博行 |
|
伝冷泉為秀未詳物語断簡考 |
野中 直之 |
|
長澤規矩也先生旧蔵 近世上方子ども絵本 |
木村八重子 |
|
『清話抄』と黒河春村 |
浦野 都志子 |
|
線装はいつ発現したか |
安江 明夫 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十八) |
新田 元規 |
|
第65号 平成26年6月 |
|
|
訓点語研究史における築島裕博士の功績と残された課題 |
小林 芳規 |
|
広開土王碑「多胡碑記念館本」の調査報告 |
武田 幸男 |
|
『萬葉集』(巻十七)の万葉仮名「し」について |
引原 英男 |
|
中山切『古今和歌集』の本文的性格 |
寺田 伝 |
|
承元四年粟田宮歌合について |
日比野 浩信 |
|
『封神演義』第九十九回の問題 |
尾崎 勤 |
|
袋綴じ装の発明と発展 |
安江 明夫 |
|
『改訂増補 漢文学者総覧』書評 |
杉下 元明 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十七) |
新田 元規 |
|
第64号 平成25年12月 |
|
|
田中教忠旧蔵本『懐風藻』について |
土佐 朋子 |
|
李嶠百詠詩題注における和名抄の利用 |
福田 武史 |
|
伝藤原為相筆『土左日記』攷・続貂 |
大島 冴夏 |
|
伝慈円筆烏丸殿切『貫之集』の本文系統 |
北井 佑実子 |
|
書陵部蔵『従二位家隆卿集』残欠本をめぐって |
舟見 一哉 |
|
王紹蘭の『潛夫論箋』補注について |
中村 哲夫 |
|
陳澧『白石詩評』過録批校本・鈔本 |
蕭 振 豪 |
|
冊子の誕生――東洋編 |
安江 明夫 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十六) |
恩田 裕正 |
|
第63号 平成25年6月 |
|
|
『大唐六典』唐令の「開元七年令」説への反論 |
中村裕一 |
|
『類要』中の『通暦』佚文について |
会田大輔 |
|
醍醐寺蔵宋版一切経の雑函に納められた経巻をめぐって |
森岡信幸 |
|
『卜筮元亀』とその周辺 |
宮 紀子 |
|
折本の起源考 |
安江明夫 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十五) |
恩田裕正 |
|
伝冷泉為尹筆四半切後撰和歌集の本文系統 |
立石大樹 |
|
古典語において接頭語とされる「うら―」についての一考察 |
山王丸有紀 |
|
『閑居友』下巻第七話と龐居士説話 |
岩山泰三 |
|
「蟭螟」補注 |
橋本正俊 |
|
第62号 平成24年12月 |
|
|
『懐風藻』未紹介写本三点 |
土佐朋子 |
|
日本古代史料に見える「揚名」の語義――『孝経』の原義との関係―― |
渡辺滋 |
|
史料としての表具 |
髙田智仁 |
|
篠屋宗礀と多福文庫旧蔵本 |
長坂成行 |
|
黒河春村の狂歌――文政時代―― |
浦野都志子 |
|
『漢書藝文志』“暦譜”の意味 |
成家徹郎 |
|
平安後期の入宋僧と北宋新訳仏典 |
大塚紀弘 |
|
陽明学の聖地に残された石刻――「天真精舎勒石」について―― |
鶴成久章 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十四) |
田中有紀 |
|
第61号 平成24年6月 |
|
|
『万葉集』(巻十五)の万葉仮名「之・思・志」と特徴について |
引原英男 |
|
『榻鴫暁筆』の『徒然草』享受 |
稲田利徳 |
|
光悦筆和歌巻に見る書の独自性 |
根本知 |
|
写本『鍾秀集』と『南海先生詩稿』 |
杉下元明 |
|
『漢武帝内伝』『天隠子』両和刻本について――大神貫道と木村蒹葭堂―― |
坂出祥伸 |
|
『菜根譚』佚条五条――明刊諸本について――(附)佚条五条訳注 |
田口一郎 |
|
朱希祖旧蔵『連環記』抄本について |
片倉健博 |
|
蔡大鼎の漢詩文集の諸本について――琉球末期の漢詩文集の刊行を中心に―― |
紺野達也 |
|
南宋越刊『易』、『書』、『周礼』八行本小考 |
李霖 |
|
鄭樵『滎陽家譜前序』について |
唐黎明 |
|
後漢時代における洛陽の文化表象についての考察――「両都賦」解読を中心に |
黄婕 |
|
『朱子語類』巻九十四訳注(十三) |
垣内景子 |
|
第60号 平成23年12<
|