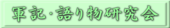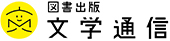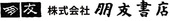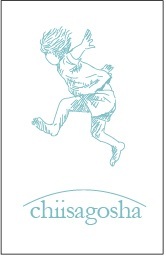71~最新号
内容説明
雑誌『汲古』バックナンバー
汲古86号 令和6年12月
国文学研究資料館松野陽一文庫蔵『うつほ物語』断簡について 髙橋 諒
『大鏡』の古筆切――「池田本」巻末散佚部分の出現―― 石澤一志
広瀬重兵衛と菅茶山 杉下元明
黒河春村『地頭名義考』について 浦野都志子
『本朝文粋』巻十詩序校訂三則 李筱硯
『諧声品字箋』に関する一書誌学的研究 孫楊洋
梁啓超と河上肇
――経済学と社会主義をめぐる両者の「接点」を探る―― 川尻文彦
『朱子語類』巻二十一訳注(九) 垣内景子
【涓涓滴滴(6)】
「紙背」から見えるいろいろなこと 櫻井 彦
新刊近刊案内
汲古85号 令和6年5月
大和綴の書写と製本 櫛笥節男
伝後光厳天皇筆本『竹取物語』新出断簡とその本文特性 岸川大航
成簣堂文庫蔵「二箇条疑問事」と裏書「安貞二年仮名法語」 森新之介
韓愈「冬薦官殷侑状」繋年試論 小野木聡
静嘉堂文庫蔵『新刊指南録』について 近藤一成
『簠簋抄』の説話――阿難入滅譚について―― 中野瑛介
『朱子語類』巻二十一訳注(八) 山本健太郎
【涓涓滴滴(5)】
土岐善麿宛吉川幸次郎書簡ならびに漢詩 兼築信行・金文京
新刊近刊案内
|
汲古84号 令和5年12月 |
|
|
日本大学図書館文理学部分館蔵『頓阿法師名所集』について |
樋口百合子 |
|
『閑窓自語』中巻第四七話「釈奠上卿毎事問人語」と『続史愚抄』 |
芝崎有里子 |
|
舟木杏庵『南遊紀事』の紹介と翻刻 |
新稲法子 |
|
小中村清矩「尾張国解文略説」について |
浦野都志子 |
|
「高勾麗好太王墓碑」―発見時期と光緒二年本の再考― |
河野雄一 |
|
馮夢龍の『中興実録』について |
大木 康 |
|
光緒十年怡怡堂刊『関帝明聖真経』と斉有堂「霊験記」について |
小谷友也 |
|
『朱子語類』巻二十一訳注(七) |
恩田裕正 |
|
【涓涓滴滴】 |
岸本美緒 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
汲古83号 令和5年6月 |
|
|
伝覚家筆『玉葉和歌集』断簡紙背の仮名暦 |
仁平道明 |
|
『野田の足穂』の翻刻と解題 |
梅田径 |
|
始皇帝の遺詔と薄葬の系譜 |
鶴間和幸 |
|
王琰『冥祥記』佚文追加の可能性 |
佐野誠子 |
|
『朱子語類』巻二十一訳注(六) |
恩田裕正 |
|
【涓涓滴滴】 |
長澤孝三 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
汲古82号 令和4年12月 |
|
|
『玉泉帖』と花押印 |
藤本孝一 |
|
明治大学図書館蔵毛利家旧蔵本『歌枕名寄』について |
樋口百合子 |
|
漢語辞書『増補新令字解』の版種について |
今野真二 |
|
山梨県立図書館蔵『薛王二先生教言』について |
永冨青地 |
|
琉球の科試関連資料 |
中野直樹 |
|
『朱子語類』巻二十一訳注(五) |
田中有紀 |
|
【涓涓滴滴】 |
兼築信行 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
汲古81号 令和4年6月 |
|
|
『夢の通ひ路物語』散逸部断簡の出現 |
上原作和 |
|
『しぐれ』永正十年絵巻の問題点 |
仁平道明 |
|
黒河春村の『尾張国解文』研究について |
浦野都志子 |
|
巻子から冊子へ―馮道の九経刊行の意義― |
池田昌広 |
|
江戸時代における叢書『説鈴』の利用についての小考 |
楊 維公 |
|
『朱子語類』巻二十一訳注(四) |
田中有紀 |
|
東京港区亀塚公園の亀山碑文について |
金 文京 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第80号 令和3年12月 |
|
|
『源氏物語』紅葉賀「仏の御迦陵頻伽の声」の解釈 |
金子英和 |
|
建仁元年『石清水社歌合』の判者 |
田口暢之 |
|
近世天草における司法構造と調整機能 |
安高啓明 |
|
『礼記』経解篇の脱簡について |
井上 了 |
|
日本における律学の受容と『唐令私記』 |
瀬賀正博 |
|
王復礼『三子定論』について |
永冨青地 |
|
『朱子語類』巻二十一訳注(三) |
新田元規 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第79号 令和3年6月 |
|
|
笑雲瑞キン『笑雲入明記』をめぐって |
西山美香 |
|
国立歴史民俗博物館蔵田中穣氏旧蔵 |
樋口百合子 |
|
黒河春村編『古物語類似鈔』について |
浦野都志子 |
|
『春秋正義』『漢書』周三十六王説と『帝王世紀』周三十七王説 |
竹内航治 |
|
中国における冊子の誕生とソグド人 |
池田昌広 |
|
明嘉靖本『新安休寧汪渓金氏族譜』から見た朱熹新出書簡について |
李 霊均 |
|
『朱子語類』巻二十一訳注(二) |
新田元規 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第78号 令和2年12月 |
|
|
伝後鳥羽天皇筆 古今集切の出現 |
岡田直矢 |
|
「倉庫堅完破」条の運用と量定基準 |
安高啓明 |
|
李鼎祖『周易集解』の流伝 |
藤田 衛 |
|
京都大学蔵王筠校祁寯藻刻『説文解字繫伝』四十巻について |
木津祐子 |
|
『独断』訳注商榷三則 |
野口 優 |
|
再び関西大学図書館所蔵手鑑『二十四孝』について |
橋本草子 |
|
『朱子語類』巻二十一訳注(一) |
恩田裕正 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第77号 令和2年6月 |
|
|
「御迦陵頻伽の声」続貂 |
今西祐一郎 |
|
浮世草子『桜曽我女時宗』の初印本・再印本と狩野文庫本 |
馬渕敬子 |
|
黒河春村著『節用集考』を巡って |
浦野都志子 |
|
前漢前半期における外戚と中央政界 |
平松明日香 |
|
『荆楚歳時記』の内容と著者 |
中村裕一 |
|
『詩人主客図』の流伝に関する一考察 |
秋谷幸治 |
|
『朱子語類』に見られる「下学上達」の熟思想と |
松宮貴之 |
|
いわゆる『晋宋奇談』について |
富嘉吟 |
|
『明律訳註』成立に関する一考察 |
宮本陽佳 |
|
朱子語類訳注(二五) |
恩田裕正 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第76号 令和元年12月 |
|
|
『源氏物語』紅葉賀巻管見 |
岡田貴憲 |
|
藤原定家とシタテルヒメ |
兼築信行 |
|
内藤記念くすり博物館大同薬室文庫蔵『歌枕名寄』 |
樋口百合子 |
|
冷泉為恭筆『年中行事図巻』の諸相 |
川島絹江 |
|
『俗語解』と『水滸伝』 |
氏岡真士 |
|
朱子語類訳注(二四) |
田中有紀 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
|
|
|
第75号 令和元年6月 |
|
|
後撰集四二五番歌の詞書本文をめぐって |
福田孝 |
|
玉虫左太夫『航米日録』の別本について |
浅野敏彦 |
|
侯康・陳澧校本『文館詞林』について |
蕭 振豪 |
|
朱子語類訳注(二三) |
垣内景子 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第74号 平成30年12月 |
|
『源氏物語』紀州徳川家旧蔵本の片鱗 |
久保木秀夫 |
|
原撰本系『玉吟集』奥書試読 |
舟見一哉 |
|
書陵部蔵福州版一切経の本文欠落巻について |
中村一紀 |
|
藤原惺窩鬼界島漂到と詩歌稿紙背文書 |
石上英一 |
|
尾張明倫堂刊本『唐丞相曲江張先生文集』をめぐって |
富嘉吟 |
|
京都大学河合文庫所蔵『遺稿』の著者について |
金文京 |
|
朱子語類訳注(二二) |
中嶋諒 |
|
早稲田大学図書館「これが連歌だ! |
兼築信行 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第73号 平成30年6月 |
|
|
松永耳庵著『桑楡録』所蔵 伝西行筆源氏集切の出現 |
岡田直矢 |
|
『雨珠記』と正応四年の紀州由良隕石 |
大塚紀弘 |
|
黒河春村『自著目録』と筆頭著録の『万葉集墨水鈔』について |
浦野都志子 |
|
プリンストン大学所蔵『顔文忠魯公文蹟』について |
宮崎洋一 |
|
朱子語類訳注(二一) |
恩田裕正 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第72号 平成29年12月 |
|
|
「栂尾類切」考 |
徳植俊之 |
|
三室戸寺蔵『謌枕名寄』について――流布本新資料の可能性―― |
樋口百合子 |
|
玄応撰『一切経音義』諸本系統から見たP.2901 |
李乃琦 |
|
浙江大学蔵竹簡『左伝』は研究資料たり得るか |
大西克也 |
|
瑞渓周鳳『善隣国宝記』及び万里集九『帳中香』所引〈宋元通鑑〉考 |
大島絵莉香 |
|
七十回本『水滸伝』の光霽堂刻本について |
氏岡真士 |
|
和刻本『忠義水滸伝』二集について――沢田一斎の関与をめぐって―― |
宮本陽佳 |
|
越南本『天元玉暦祥異賦』について――天文五行占書伝播の一例として―― |
佐々木聡 |
|
朱子語類訳注(二〇) |
田中有紀 |
|
新刊近刊案内 |
|
|
第71号 平成29年6月 |
|
|
国立歴史民俗博物館蔵高松宮旧蔵『源氏物語聞書』(『源秘抄』)について |
酒井茂幸 |
|
国立国会図書館蔵『清水の冠者』攷――挿絵紙背を巡って―― |
戸島みづき |
|
黒河春村と索引 |
浦野都志子 |
|
文字学からみた浙江大『左伝』偽簡説の問題点 |
小沢賢二 |
|
嘉興市図書館蔵周氏万巻楼刊『萬寶全書』について |
玉置奈保子 |
|
尊経閣文庫所蔵の明版『聖朝破邪集』について |
永冨青地 |
|
鎮江本『大易断例卜筮元亀』小識 |
伊藤裕水 |
|
朱子語類訳注(一九) |
小池 直 |
|
新刊近刊案内 |
|