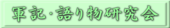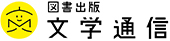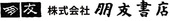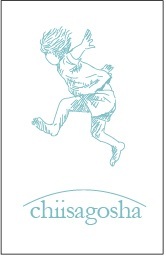目次
第一部 内史・三輔・関中編―「本土」から「首都圏」へ
第一章 内史の展開と秦漢統一国家体制の形成
雲夢秦簡と内史研究/「二年律令」と内史研究/里耶秦簡、岳麓秦簡と内史研究/内史制度の展開と秦漢統
一国家体制の形成
第二章 前漢三輔制度の形成
三輔制度形成をめぐる史料と先行研究/三輔成立の時期をめぐって/内史分置の文帝後元年間説をめぐって
補論 『漢書』地理志における内史の設置時期をめぐって
『漢書』地理志に見える各郡国の設置時期/黄彰健説の検討
第三章 前漢三輔制度の展開 三輔都尉/関中の拡大/司隷校尉部の出現
第四章 中国「畿内制度」の形成に関する一考察
秦・漢初における「畿内」/翼奉の洛陽遷都論/王莽の畿内制度
第五章 関中・三輔・関西―関所と秦漢統一国家―
国内の関所のライン/秦および前漢前期における「広域関中」と「初期領域」、「内史の地」の呼称の用例/
前漢後期における「新関中」と三輔地域の呼称の用例/後漢期における「関所の内側」と三輔地域の呼称の
用例
第二部 東方諸地域編―「他国」から「地域」へ
第一章 統一前夜―戦国後期の「国際」秩序―
戦国後期の「統一国家像」/戦国後期の「国際」秩序/「国際」秩序から統一国家体制へ
第二章 燕・斉・荊は地遠し―秦漢統一国家と東方地域―
問題のありか―統一国家体制の形成と展開―/秦末、楚漢戦争期の東方地域/漢初における各諸侯王国の地
域的傾向
補論 戦国の残像―秦末、楚漢戦争期における旧魏の領域―
『戦国縦横家書』第二十六章に見られる魏の領域とその年代/秦末、楚漢戦争期における旧魏(梁)の領域
/終節―戦国の残像―
第三章 使者の越えた「境界」―秦漢統一国家体制形成の一こま―
前漢武帝期における統一国家体制の形成―近年の研究から―/徐偃矯制事件の周辺/元狩・元鼎の交―博士
の郡国循行の事例から―/終節―「境界」を超えて―
第三部 移動と空間編―軍事、行幸
第一章 秦代国家の統一支配―主として軍事的側面から―
秦末・楚漢戦争期の軍事的状況/統一支配の軍事的背景/統一支配の軍事的体制
補論 三川郡のまもり―「秦代国家の統一支配」補論―
三川郡の概観/三川郡のまもり/終節―秦代国家の統一支配・補論―
第二章 新朝の統一支配―主として軍事的側面から―
前漢の統一支配と翟義の乱/四関将軍/新朝の防衛体制―崩壊時の事例から―
第三章 前漢武帝期の行幸―その基礎的考察―
行幸資料の集成/行幸の概要/行幸と地域/行幸の諸相/終節―歴史的位置づけ―
第四章 後漢時代の行幸 行幸の概要/行幸と地域/行幸の諸相
終 章 ここまでのまとめ/秦邦―戦国後期の「国際」秩序と領域内での地域的区分―/統一秦における領域
内での地域的区分/秦漢統一国家体制の形成と展開
補論 「襄武・上雒・商・函谷關」の間―岳麓書院蔵秦簡(肆、五三)に見える特定領域―
特定領域の範囲とその問題点/特定領域をめぐる諸研究の検討
引用文献一覧/初出一覧/あとがき/索引(歴史人名・事項・引用史料・研究者名)
内容説明
【序章より】(抜粋)
中国の長い歴史において、時として分裂の局面をまじえながらも、基本的に統一の枠組が維持され、かつ拡大、発展してきたことは、その大きな特徴の一つといえるであろう。本書では、そこでの最初の事例となる秦および漢代における統一国家の体制がいかに形成され、かつ展開していったのかを、主として「地域の統合」――すなわち「地域間での支配、対立関係の構図とその相対化」――という側面より考察を加えてゆくものである。
秦漢時代、とくに秦および前漢時代の統一国家における「地域間での支配と対立の関係の構図」は、基本的に都の置かれていた西方の地域が東方地域を支配するというものであった。……筆者はこうした関係の統一国家の構造におけるあらわれ方を(狭義の) 「統一国家体制」として、その形成や展開について、これまで考察を重ねてきた。それらはおよそ以下のような三つの論点に分けることができる。
まず一つ目は、統一支配の基盤となる「支配、統合する側の地域」、いわば「中核地域」の国制上の位置づけの問題である。(中略)二つ目の論点ではこれとは対照的に、統一国家形成の過程において「支配、統合される側の地域」となった東方地域のあり方を問題とする。(中略)最後に三つ目の論点として、こうした地域間の関係を背景に展開される統一国家支配の実態について、反乱軍や鎮圧軍、あるいは皇帝による移動の事例から、具体的に考察し、確認したのであった。
……こうした検討を通じて、この中国史上最初の本格的な統一が成立し定着してゆく過程やその構造をある程度具体的に一貫したかたちで理解するとともに、そこで展開し、関連してくるこの時代の諸相についてもつとめて明らかにしてゆくこととしたい。
このような見通しのもと本書では、旧稿に増補、改定を施し全体の論旨を整えた上で、それらを上記三つの論点に応じてそれぞれ第一部「内史・三輔・関中編」、第二部「東方諸地域編」、第三部「移動と空間編」の諸章としてまとめて構成している。これをうけてさらに「終章」では、各時期における「地域間の支配、対立関係の構図」のあり方を時系列に沿って提示した。ちなみに本書では、第一部第一章第四節や第五章第三節、あるいは終章をはじめとして、現在公表が進んでいる里耶秦簡や岳麓書院蔵秦簡、とくに後者の最新の成果を取り入れている。