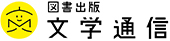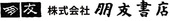目次
序章 近代書学をめぐる「知」の問題
第一部 前近代からの接続
第一章 翁方綱にみる名品の書流―『化度寺碑考』を手がかりとして―
小序
第一節 研究史の概要 第二節 京大本の書誌
第三節 翻刻「化度寺碑銘筆法攷」 第四節 翁説における「筆法攷」の位置
小結
第二章 翁方綱の北碑観―兼ねて阮元説との関係に及ぶ―
小序
第一節 「上承隷意、下啓唐楷」論について 第二節 翁における南北書派
第三節 翁における北碑の優品
小結
第三章 翁方綱・阮元と清朝書学の転換―「帖学期」・「碑学期」を超えて―
小序
第一節 翁方綱説対阮元説 第二節 嘉慶期以後
第三節 王澍説への遡及
小結
第二部 碑学の相対化と変容
第四章 碑学盛行後の帖学―陶濬宣「宋元祐秘閣本晋唐小楷帖跋」の碑帖互証―
小序
第一節 『稷山文存』の書誌と「宋元祐秘閣本晋唐小楷帖跋」の翻刻
第二節 「元祐秘閣本晋唐小楷帖」について
第三節 陶跋の背景 第四節 近代北碑論としての陶跋
小結
第五章 李瑞清の金文書法論―「玉梅花盦論篆」とその系譜―
小序
第一節 「論篆」の概要・構成 第二節 「論篆」をめぐる資料的環境
第三節 「論篆」各派の体系 第四節 近代碑学における「論篆」
小結
第六章 『流沙墜簡』の書法的受容―羅振玉・沈曾植から沙孟海まで―
小序
第一節 羅振玉・沈曾植の交誼 第二節 『沈乙盦尚書手簡』の書誌と部分翻刻
第三節 『流沙墜簡』中の羅振玉の書法論 第四節 沈曾植の『流沙墜簡』書法論
第五節 李瑞清・曾煕・鄭孝胥 第六節 康有為・梁啓超・姚華
第七節 沙孟海
小結
第三部 書学資料の鑑蔵と複製
第七章 端方が目指した碑拓鑑蔵の拠点化―碑拓著録『匋斎蔵碑跋尾』とその寄跋者たち―
小序
第一節 著録文献としての『跋尾』 第二節 『跋尾』寄跋者の陣容
小結
附節 端方における所蔵碑拓の改装
第八章 時代を映す碑拓鑑定指南―方若『校碑随筆』の周辺―
小序
第一節 「方著」の創新 第二節 「方著」に対する褚徳彝の疑念
第三節 羅振玉と「方著」
小結 附節 楊宝鏞の試みと「方著」
第九章 刻帖から影印帖への転換―趙爾萃『傲徠山房所蔵五朝墨迹』の誕生―
小序
第一節 『傲徠』の書誌と内容・構成 第二節 趙爾萃と中裕洋行
第三節 転換期における『傲徠』
小結
第十章 筆写文字資料の影印に対する近代的認識の一斑―鄧実の出版活動を例に―
小序
第一節 鄧実による筆写文字資料の影印出版物 第二節 鄧実の影印出版の周辺
小結
第四部 「美術」の導入と中国書学
第十一章 清末国粋派における「美術」と「金石書画」―劉師培から鄧実へ―
小序
第一節 『学報』初期の「美術」 第二節 「美術篇」における劉師培の視点
第三節 鄧実と「金石書画」 第四節 「美術」と「金石書画」の行方
小結
第十二章 「整理国故」運動の「美術」と「書」への波及―陳彬龢『中国文字与書法』の啓示―
小序
第一節 陳彬龢と『国学小叢書』 第二節 『書道』の選択
第三節 書の整理の幅と漸次性
小結
第十三章 書を編み込んだ中国美術通史―清末の雑誌論文、民国期の教科書―
小序
第一節 ささやかな復活 第二節 時代が要請した教科書
第三節 劉師培の未完稿 第四節 国学と書
小結
附節 鄭昶・史岩の美術通史における書法史の典拠
第五部 中国書学を介した日中交流
第十四章 羅振玉と明治末葉の東京―交友録としての「扶桑再遊記」―
小序
第一節 訪日の梗概 第二節 交流を支えるネットワーク
第三節 帰国後の交流
小結
第十五章 博文堂における中国法書の影印出版について―内藤湖南と羅振玉のアプローチ―
小序
第一節 先行研究と本章の視点 第二節 初期の中国法書影印出版と内藤湖南
第三節 羅振玉参画後の内藤湖南 第四節 羅振玉における流入品の購得と周旋
第五節 羅振玉の法書影印出版観
小結
第十六章 敦煌本温泉銘の書法に対する内藤湖南の見解―内藤の交友と王羲之書法観を視野に―
小序
第一節 内藤の敦煌本温泉銘書法論 第二節 内藤の渡清と書法談義
第三節 王羲之各書跡の影印に寄せた内藤の題跋 第四節 各跋に展開する諸論点
第五節 基本的論点における定見の不在
小結 附節 内藤湖南と敦煌文書写真展
結章 「知図」で展望する近代書学
あとがき
内容説明
【序章「近代書学をめぐる「知」の問題」より】(抜粋)
中国に誕生し、東アジアを中心に今なお発展を続ける「書」――その持続的発展の土壌に、書の学び、即ち「書学」の存在を見出すことは、さして困難ではない。所謂「手習い」もその学びの一つであって、書は学ぶものという観念が広く定着し、書と書学が表裏をなしつつ歩みをともにしてきた意義は大きい。北宋の徽宗皇帝は、内府に「書学」及び「画学」「算学」「医学」と称するそれぞれの教習所を設けたという(『宋史』徽宗本紀)。ここで書と画が並置されたことは、少なくとも北宋までに、書が今日の造形芸術に相当する領域として認識されていたことを物語る。それを「書学」と称するところの実際は、実技を主体とした学びであったろう。ただし、書学の到達目標が優れた書作にあったとしても、それへの過程には様々な学びが関わってくる。本書が射程とする書学とは、専らこうした学び、即ち実技・書作に通底しつつ、成果としては独立する知的営為であり、具体的には知見の言説化(書論の執筆)や、資料組織(作品の鑑蔵や展覧、または図録・著録の編成・出版)の類である。そうした書学が、時代とともに内容を拡充してゆくことは、歴代の名跡の累積からしても言を俟たない。のみならず、折々の書学が動的であることには、書を取り巻く種々の学知の影響もある。特に本書が関心を寄せるのは、近代のそれである。
昨今、「近代知」の枠組による思想史研究・人文学研究が、日本や中国、延いては東アジアを視野 に顕著な成果を挙げている。「近代知」を術語として掲げないまでも、東アジアにおける「近代」と「知」との固有の結び付きに着目する研究は、頓に盛行している。それら先学の問題意識は、古代から近世までの各時代の知と単純に並列し得ない「近代知」の特殊性に向けられている感がある。中国を例に見ても、清末の列強進出から辛亥革命を経て、中国共産党の新国家建立に至るまでの動乱の連続は、過去の如何なる時代にもまして、多様な趨勢の錯綜とその時間的な濃縮とを如実に示している。それに伴う学知の形成も、所謂「西洋の衝撃」から、洋務運動、変法運動を経て新文化運動やマルクス主義に至るまで、幾重にも奔流をなして押し寄せるが如くである。かかる奔流の渦にあって、如上の先学はその分析対象を狭隘な思想史的事象に限定することなく、時の学術・文化諸般を広く視野に収める中で象徴的な個別事例に求めた。各事例の多様な学知を横断的に比較検討することで、「近代知」の核心に迫ったのである。加えて先学は、たとえ一国の事例を対象とするにしても、国域を超えた学知の往還に意を払ってきた。そこには、漢字・漢語の国際的な共有が不可避的な論点として介在している。
本書が検討対象に据える近代中国の書学は、先掲の条件から比較的明瞭な輪郭を持っている。だが、その書学に影響を与える学知が、上述のように幾多の思潮を形成しつつ多様な変遷を遂げるとなれば、これに応じた書学の中身は必然的に一律ではなくなる。例えば、書は何を学ぶのかという最も基本的な問題においても、それは史学の資料となる出土文献から切り離すことはできず、時に西洋の主導で考古学的に発掘された西域肉筆文書は、書学にも重大な変革をもたらした。また例えば、歴代書法を回顧し、「中国書法史」を構想するに際しても、書を如何なる学知(学科)とどのように関係付けるのかによって、その捉え方は変わってくる。これらを踏まえ、本書では、近代書学が時の学知(近代知)の諸相に応じ、そのあり方を多角的に更新してゆく軌跡について、その大局的な把握を一つの目標としたい。この目標はもとより遠大であり、当該の書学を網羅的に収集し、それらの分析を逐次積み重ねるような定石に則れば、容易に到達し得ない。故に、こうしたテーマを一著にまとめ上げることは、極めて困難な試みと言わざるを得ず、本書はその大仰なタイトルからして、「羊頭狗肉」の誹りを免れまい。だが、本書は上述の先学が敢えて絞り込んだ事例に基づき、多方面に亘る近代知の大局を的確に点描・素描してきたことに、大いなる可能性を見出している。これら先学に倣い、本書では種々の近代知との密接な関わりが確認できる典型例を精選し、重点的に分析を加えるという手法を採ることにした。