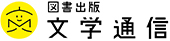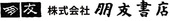目次
§1 中国語音韻史の時代区分
§2 『切韻』と『廣韻』
『切韻』序文
『切韻』の性格
『切韻』の基礎音系問題
切韻系韻書
『廣韻』
切韻系韻書の体例――『廣韻』を例として――
§3 反 切
反切以前の漢字標音法
反切の構成
反切の“口唱性”
反切の起源
§4 『廣韻』反切の分析
『切韻』代用としての『廣韻』の反切
反切用字は何故変わるか
反切系聯法
反切系聯の実際
反切系聯結果に対する解釈の必要性
§5 韻 図
『韻鏡』と『七音略』
転図の構成/転図への韻の配置
『韻鏡』『七音略』の転図配列順
『韻鏡』制作の目的
『韻鏡』のテキスト
反切系聯結果の解釈
§6 中古音の音類
韻母/声母
転図の等位と声母・韻母の配置
音類による中古音の表記
§7 音価推定
現代諸方言音
外国漢字音
梵漢対音と蔵漢対音
音価推定の方法とKarlgrenの業績
音価推定の実例
音価表
§8 推定音価に関する若干の問題点(一) 重紐をめぐって
重紐の存在
重紐の音価
重紐の音価についての諸説(有坂・河野説以外)
重紐の一方のみを含む韻
重紐韻における端系・知系の韻母音価
重紐を含まない三等韻の場合
拾遺
§9 推定音価に関する若干の問題点(二) 反切上字の用法からの推論を中心に
切韻反切の上字用法
敦煌毛詩音反切の上字用法
声母“j化”の問題
四等専属韻の音価
之韻の音価
蒸職韻の音価
魚韻の音価
円唇的軟口蓋音韻尾について
§10 声調調値
§11 中古音の音韻論的解釈
§12 六朝末・唐初の南方標準音
§13 唐代の音韻変化
音類の変化――慧琳音義以前
音類の変化――慧琳音義
音価の変化
変化の理由について
唐末の音韻・音声変化
§14 現代北京語との対応
声母
韻母
声調
§15 対応規則の例外
例外の原因
文語音と白話音
中古音と祖語の体系上のずれによる見かけの例外
参考文献
あとがき
索引
内容説明
【本文より】
「中古音」とは、狭義では、『切韻』(隋の仁壽元年、601年)という韻書に反映している音韻体系を指し、広義では、南北朝から北宋あたりまでに至る間の音韻体系(その間にもおのずから変化があるが)を包括してあらわす。
音韻史とは、発音の歴史というほどの意味である。通常“発音”という時、それには二つの意味がある。一つはある時代のある言語(方言)における音韻体系、及びその表現としての発音習慣の総体、という意味である。……今一つは、個々の単語(形態素)の語形という意味である。……勿論この二つの意味は互いに依存する関係にある。単語の語形はその言語の音韻体系に含まれる音を組み合わせて構成されるものである。逆に音韻体系は、その言語に存在する総ての単語の語形を集めて、それらをできるだけ単純に、過不足なく説明できるように仮定されたものである。普通、音韻史という場合、それは音韻体系の歴史を意味するが、その背後には個々の単語の語形の変遷史が含意されている。
【あとがきより】
本書は、私が1980年代から1990年代にかけて主に東京大学で行った講義「中古音講義」の記録を、岩田礼、太田斎両氏の助力によりまとめたものである。
講義録は私がワープロで作成した原本のほか、竹森牧人氏(元青森県高校教諭)が再入力し、参考資料を付したテキストがあり、本書は後者に基づいている。竹森氏作成の参考資料は、画像ファイルとして本文中に挿入されていたが、本書では改めてすべてをWORD形式で再作成し、通し番号を付した表とした。また、一部の表は、講義中に配布された他の資料(主に太田斎氏が所蔵するもの)に基づいて作成した。作表の多くは、島川愛理氏(金沢大学中国語学中国文学研究室卒業生)が行ったと聞く。参考文献は、原本において書誌を付して本文中に挿入されていたが、本書では、一部を除き、著者名と書名・論文名のみ残し、書誌は参考文献(太田斎氏作成)としてまとめて示した。……中国音韻史研究を志す後継者にとっての道しるべとなれば幸いである。
関連記事
- 『平山久雄 中古音講義』「正誤表」(第三版) - 2022.09.28