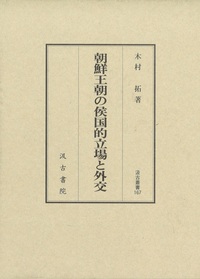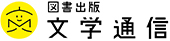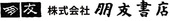目次
序章 本書への導入
一 本書の目的
二 先行研究の議論とその限界
三 本書の構成と概要
(一)第一部――朝鮮の外交論理・秩序――
(二)第二部――朝鮮の外交と「私交」問題――
(三)終章――一七世紀前半朝鮮の対日本外交の変容――
第一部 朝鮮の外交論理・秩序
第一章 朝鮮世宗代における女真人・倭人への授職の対外政策化
一 授職の対外政策化前史
(一)五衛職授与への一本化
(二)向化受職人の待遇
二 授職の対外政策化とそれ以後
(一)授職目的の変化――侍衛から羈縻へ――
1女真人の場合
2倭人の場合
(二)授与官職の変化――実職から散職へ――
三 女真人・倭人の官教における印の変更とその意味
補 論 朝鮮の国王印と侯国的立場
第二章 朝鮮による女真人酋長への授職と羈縻――明の品帯を超えて――
一 女真人羈縻における品帯の意味
二 都万戸授与による女真人酋長の羈縻
(一)女真人への万戸職授与の再開
(二)酋長への都万戸授与と明の金帯
第三章 朝鮮による女真人・倭人への授印政策
一 印信と図書
二 女真人・倭人への授印政策の意味
(一)女真人への授印信
(二)倭人への授図書
三 女真人・倭人への授印政策と侯国的立場
第四章 朝鮮の対馬認識の体系的考察――一五世紀を中心として――
一 朝鮮の対馬認識の変遷
(一)高麗末期から己亥東征までの対馬認識
(二)己亥東征前後における対馬認識の変化
二 朝鮮の「藩籬」としての対馬の性格――豆満江流域の女真人集落との対比から――
第五章 朝鮮の対日外交秩序の新たな理解――『海東諸国紀』を手掛かりとして――
一 『海東諸国紀』のなかの「日本国」
二 対日外交秩序における「日本国」
(一)進上・粛拝儀礼と「日本国」
(二)授図書の制度と「日本国」
三 対日外交秩序の新たな理解
(一)朝鮮の主張した二つの対日外交秩序
(二)明中心の国際秩序との関わり方
第二部 朝鮮の外交と「私交」問題
第六章 朝鮮初期における室町幕府への遣使の目的
一 太祖・定宗代――頻繁な使節往来までの前史――
二 太宗代――倭寇対策のための遣使――
(一)頻繁な使節の往来
(二)室町幕府への遣使の途絶
三 世宗代――「交隣の礼」履行のための遣使――
(一)初期三度の回礼使の派遣――宋希璟・朴熙中・朴安臣――
(二)通信使朴瑞生の派遣
(三)回礼使李藝・通信使高得宗・通信使卞孝文の派遣
四 室町幕府への遣使の再途絶
第七章 一五世紀前半朝鮮の対日「交隣」と「私交」
――明に送られた世宗の行実を手掛かりとして――
一 明の「東藩」の立場と対日通交
二 明の「東藩」の立場と「私交」・「交隣」
第八章 朝鮮世宗による事大・交隣両立の企図
一 世宗による被虜明人張清らの送還の意味
(一)事大の礼に基づく被虜明人の送還
(二)事大と交隣の矛盾の解消
二 交隣使節の接待をめぐる世宗と臣下の立場
(一)日本使節の場合
(二)琉球使節の場合
第九章 朝鮮の交隣文書における図書使用の理由
一 書契における印の選択
二 世宗による印信使用の提案の意図
三 図書使用と「私交」問題
(一)「私交」問題をめぐる世宗と臣下の対立
(二)図書使用による「私交」問題回避の論理
終 章 一七世紀前半朝鮮の対日本外交の変容
――「為政以徳」印の性格変化をめぐって――
一 対日本国書と「為政以徳」印
二 「為政以徳」印の性格変化――図書から璽宝へ――
三 対日本外交の変容――国書の「公文書」化――
(一)明の権威を借りた対日本外交
(二)対日本外交における「天の申命」の登場
(三)対日本国書における璽宝の使用
引用文献一覧
あとがき
索 引
内容説明
【序章より】(抜粋)
明中心の公定的世界観においては、朝鮮は「諸蕃四夷」・「外夷」の一国として位置づけられており(『大明会典(正徳版)』巻一〇一、礼部六〇、給賜一/『大明一統志』巻八九、外夷)、朝鮮はその他の周辺諸国と同列に「夷」として固定されていた。こうした明中心の公定的世界観は漢族(種族)・中原(地域)を「華」と見なす華夷観に基づいていると考えられるが、朝鮮はそうした明中心の公定的世界観を横目に見ながらも、文化を基準とする華夷観、より直截的には儒教的な「礼」の存否を基準とする華夷観を信じ、「華」への志向を強く持つようになった。そして、その「華」への志向が朝鮮を儒教的な礼制に立脚した国家体制・社会秩序の確立へと押し進めたのであるが、そうした中で同時に重視されたのが侯国的立場であった。朝鮮が理想とした国際関係は、孔子が著したとされる『春秋』の示すところの「礼」や「道」に敵う国際関係であった。そこでは、周の天子が治める畿内および諸侯国で形成される世界が「華」であり、その外側に「夷」の世界が広がっていたのであり、侯国であれば「華」の一員となり得た。朝鮮は、こうした世界観を前提として「華」への志向を強め、侯国的国家体制の形成を目指すようになり、その結果、朝鮮の対明事大は〝構造としての事大〟という形をとるようになったと考えられる。……朝鮮で「事大交隣」という成語が頻繁に用いられていたことからも分かるように、朝鮮の外交は事大で完結するのではなく、朝鮮は日本・琉球・女真人に対しても交隣などと称して外交を展開させていた。朝鮮の対明外交においては、朝貢使節の派遣回数や持参する貢物の内容に関して、明の指示があるか、あるいは明との交渉の中で決められたし、朝鮮の使節が明に赴いて執り行う儀礼や、明の使臣が朝鮮に来た際の迎接の仕方も明の定めるところがあった。また、明に送る外交文書についても一定の様式が決まっていた。このように、朝鮮の対明外交については、基本的には所与の規定が存在したと言ってよく、朝鮮はその所与の規定に則って対明外交を行うことで、対明関係においては侯国的立場を保つことができた。しかし明の志向した国際秩序は、中国とその周辺諸国との間の二項間関係の束でしかなく、そこには周辺諸国間の横方向の秩序を安定させるような機制は存在しなかった。だとすれば、朝鮮は対明事大以外の外交――日本・琉球・女真人に対する外交――を行おうとする際、侯国的国家体制のあり方を自主的・創意的に追究したのと同様、その形式や方法なりを自ら考究していかなければならなかったはずである。それでは果たして、朝鮮の日本・琉球・女真人に対する外交には、朝鮮の侯国的立場が如何なる形で反映されたのであろうか。この問題の解明によってはじめて、明代における朝鮮の国際的立場を理解できるようになり、ひいては当代の東アジア国際関係の中に朝鮮の外交を位置づけることができると考えられる。本書の目的はこの問題の解明に収斂される。
『Chosŏn dynasty’s stance as a vassal state in the diplomacy』 Kimura Taku