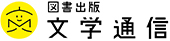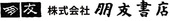目次
一 衞聚賢氏の孔子『春秋』經製作説
二 孔子『春秋』製作説の批判――戴晉新氏の説
三 趙生群氏の「孔子『春秋』製作説」肯定論について
四 總 括――『魯春秋』と『春秋』經――
第二章 『春秋』傳義の成立――『穀梁傳』に關するその學説史的展開――
一 孟子と『春秋』――『春秋』傳説の成立――
二 『春秋穀梁傳』の成立
(一)『穀梁傳』古文説
(二)『穀梁傳』成立の經緯
(三)秦・漢初の『穀梁傳』
第三章 雲夢秦簡『編年記』と『秦記』――秦代春秋學の一斷面――
一 雲夢睡虎地秦墓竹簡『編年記』
二 『編年記』の作者「喜」に關する論爭
三 『編年記』の記述形式
四 喜の生涯
五 『秦記』の記録法について――もう一つの春秋學史――
第四章 『白虎通義』 と後漢の儒學
一 『白虎通義』とその周縁
(一)『白虎議奏』と『白虎通義』
(二)章句の學
二 『禮記』王制篇から『白虎通義』へ――緯書説の流入――
三 白虎觀會議の判定方式(一)――『春秋公羊傳』義の優位
四 白虎觀會議の判定方式(二)――『春秋公羊傳』と「春秋傳曰」
五 經義の變更と新たな意義づけ
六 「尊尊」としての君臣の義
七 天と後漢王朝
第五章 許愼の『五經異義』について
一 許愼の生涯
二 『五經異義』著作の意圖
三 「春秋傳」から「春秋説」へ
四 「公羊」「左氏」説と許愼
第六章 鄭玄と何休の『春秋』論爭――鄭玄の『發墨守』『鍼膏肓』『起廢疾』を中心として――
一 何休と鄭玄
二 何休の『左氏』『穀梁』批判
三 鄭玄の何休説批判とその『春秋』解
第七章 桓譚『新論』の春秋學
一 『新論』と『春秋』
二 『新論』の春秋學(上)
三 『新論』の春秋學(下)
第八章 王充の思想形成と『春秋』
一 奇妙な生涯
二 『論衡』と『春秋』
三 王充と『春秋』及び『春秋』三傳の關係
四 想像的解釋の獲得
第九章 王符の『潛夫論』――社會批判としての儒教――
一 儒學の構圖
二 漢朝の事情と王符の現在
三 「愛日」の思想
四 赦贖の非道
五 賢者の認識
第十章 荀悅の『漢紀』と『申鍳』について――春秋學から鑑戒へ――
一 生涯と『漢紀』『申鍳』の著成
二 『漢紀』の訓戒とその形式
三 忠義への偏執
四 『漢紀』から『申鍳』へ――『申鍳』「時事第二」の構造――
五 獻帝へのアフォリズム
あとがき
索 引
内容説明
【本書より】(抜粋)
本書では十篇の論文が收められ、その内既出の論文は二篇であり、しかもその二篇とも改修ないし大幅な加筆が施されており、それ以外の八篇はいずれも初出であって、本書の體裁はほぼ世にいうところの「書き下ろし」に近い。或いは、本書は私が後漢の儒教をどのように見ているかを世に示す初めての機會であるかもしれない。そうであれば、本書は先に刊行した私の『秦漢儒教の研究』の姉妹篇とも目されよう。その意味では、本書のタイトルも「後漢の儒教と『春秋』」とすることが相應しかったのかもしれない。けれども、私はそれを敢えて「後漢の儒學」と改めた。儒教經典の解釋學が中心であるから「儒學」が似つかわしいとの思いは勿論あった。けれどもそれ以上に私には、たわいもないこだわりであるが、そうしなければならない私なりの理由があったのである。
前漢の儒教が展開する場は、國家權力の構築や治世・統治のための、體制側の權威づけであることが多かったように思う。しかもその場合の儒教は國家權力を威嚴として纏い、權力の嚴酷を徳教の禮貌で裝うもので、王朝權力の構築にも關與したことから、儒者各々の見解は國家の奉ずる儒學すなわち「經學」として奉じられるに止まって、儒者自身の獨創性が儒教の教義に新生面を切り開くことは、前漢末の揚雄を除いてほとんど稀であった。せいぜいそれまで自身が奉じた經書の威嚴を絶大視してこれを墨守しようとするのが關の山であった。それに對して後漢の儒教は儒者自身の獨創性に富んでいる。後漢の儒教は確かに課題が朝廷よりもたらされているが、それに對する解答は儒者個人の問題意識や思索によってなされることが多い。そのようになった直接の原因を尋ねれば、前漢末年の儒者揚雄の活動からの影響は見落としにできまい。揚雄における『太玄』『法言』等の經典の著作は、自身の知見を以て孔子の識見に挑んだ一大奮起の産物ではあったが、けれどもその一大奮起こそは後漢の儒者、なかんずく桓譚や王充に影響し、自身の見識が決して聖人孔子に比して劣るものではないことを自覺させた。そして自身の見解やその創意を他者に示して何ら羞じることのない主體性を獲得させ、彼等の儒教に自己固有の獨創性をもたらすことになった。その他者に示して何ら羞じることのない主體性が、延いては後漢の他の儒者達にも廣まって、自らの見解の確實を信じ、それを自由に語る個性豐かな儒者の登場を促したのではないか。そうであればそうした彼等覺醒された儒者達の活動はその主體的意識の産物であって、これを儒教や經學と呼ぶのには無理があろう。私はその彼等の活躍の地を儒學と呼んで、そこでの彼等の活動がいかなる意義をもつものであったのかを見定めようとしたのである。また、自らの知見を以て孔子の見識に挑み、孔子に匹敵するか勝ることによって自身の知見の正當を意識し、自身の主體的判斷の正確を期す儒教は、主に桓譚・王充等の春秋學中に多く認められるところから、私は後漢における儒學の展開を特に春秋學との關係で捉えなければならないことの必要性を覺えたのである。
Confucianism under the East Han Dynasty and the Spring and Autumn Annals