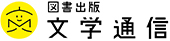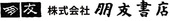目次
Ⅰ 林羅山の「文」の意識
一 「読書」と「文」
二 藤原惺窩『文章達徳綱領』の構成とその引用書――『文章欧冶』等を中心に
三 文評――「左氏不及檀弓」の論
四 「書、心画也」の論
Ⅱ 林羅山の朱子学――『大学諺解』『性理字義諺解』
一 『大学諺解』の述作の方法と姿勢
二 『性理字義諺解』の述作の方法と引用書――『文章欧冶』等を中心に
三 林羅山『性理字義諺解』と松永尺五『彝倫抄』
四 『性理字義諺解』と朝鮮本『性理字義』の校訂
五 朝鮮版晋州嘉靖刊本系統『北渓先生性理字義』五種対校略考
六 ハーバード大学所蔵朝鮮版『性理字義』――その林羅山旧蔵本説をめぐって
七 『性理字義』の訓点を通して見たる羅山・丈山の読解力
Ⅲ 日本漢学諸論
一 桂菴玄樹の四書学と『四書詳説』
二 江戸時代の訓法と現代の訓法
三 「なる世界」と「つくれる世界」――不干斎ハビアンの朱子学批判をめぐって
四 「芭蕉」という俳号をめぐって――漢文学雑考その一
五 浅見絅斎と日本儒学史研究
六 井上哲次郞の「性善悪論」の立場――「東洋哲学」研究の端緒
七 井上哲次郞の「東洋哲学史」研究
八 漢文学の在り方――その二重性
付 『漢文學 解釋與研究』編集後記
Ⅳ 先学の風景――人と墓
一 藤原惺窩
二 吉田素庵
三 堀 杏庵
四 松永尺五
五 鵜飼石斎
六 宇都宮遯庵
七 山井崑崙
八 羅山長子 林叔勝
九 桂菴玄樹
あとがき
編集後記
内容説明
【あとがき より】(抜粋)
本書は、『日本漢学研究試論――林羅山の儒学』と題した。その意図するところを述べて、「あとがき」としたい。本書に収載した論考のうちには、林羅山に関するものが多い。それを、『林羅山の儒学――日本漢学研究試論』としなかったのは、羅山の一連の論考も「日本漢学研究」を意識したものであることを強く表明したいためである。私が「日本漢学」という名称を意識したのは、学生時代、大修館『中国文化叢書』において、中国思想・中国文学等と並んで、「日本漢学」の名称のもと一巻を立てたのを目にしたのに始まる。ただ、自らが積極的にこの名称を用いるまでには、紆余曲折を経て来た。とくに一つには、明治以来の中国学研究の展開における「漢学」をめぐる議論・評価をじっくり検証することが必要と思われた。また一つには、「中国学」(中国哲学)出身の私が、上智大学文学部国文学科に赴任し、その「漢文学」の教育研究を担当する中で、中国学と漢文学との関係と違いを否応なく問うことになった。上智では、大学以後博士課程まで国文学・国語学・漢文学が鼎立された教育姿勢を持っていたことに教育研究の実践において、強く責任を感じた。その漢文学にこだわっているうちに、十数年経ち、「漢文学」専攻の院生が生まれそだち、思いきって大学・学部とは関係なく、自ら漢文学研究会の名のもと、平成十年(一九九八)秋、『漢文學 解釋與研究』を刊行、広く世に問うことにした。国内の中国学の関係学科が自覚的に外国研究との立場を鮮明にし、他方、国文学科(日本文学)の担う漢文学が漢詩文に傾きがちであることをふまえて、あらためて「漢文学」についてささやかな自己主張を試みるものであった。
……羅山の研究には各分野から多様なアプローチがある。私が意識的に羅山を対象にしたのには、中世・近世といった区分を前提にせずに鎌倉室町期から江戸中期を通して、宋元明の中国の学芸の受容と展開を捉えたいという思いがあったからである。羅山はまさに室町・江戸の接点の人であった。そして歴代有数の読書の人であり、典籍の読解を通してその学問を形成し、その表現も身につけた。その範囲は漢籍・国書を広く渉猟し、中国・朝鮮さらには西欧の思弁にも触れた。宋元明の諸書の受容は明末期刊行の書物にも及んでいる。羅山を出発点にしながら、宋元明の諸書をどのように受容したのかの推論を心掛けつつ、中国の学芸の受容とその展開を捉え直すことを意識したのである。いったい、中世・近世・近代の区分の有効性はともかく、近世・近代の区分のもと、江戸期・明治期を截然と分けて見るのと同様に、中世・近世の区分を前提に江戸期を切り離して見るならば、最初から自ら壁を作ることになりかねない。
……私のここに集めた拙稿は、まさに試論以外の何物でもないと認識せざるを得ない。所期の目的からすれば、やっと研究は緒についたばかりである。ただ思想史研究はある意味、己の今の自己研究の作業でもある。本書を出すことも、自らの思想史研究の自己確認である。