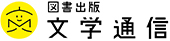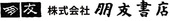目次
第一章 大道の中――徐幹『中論』の思想史的位置――
第二章 経国の大業――曹丕文章経国論考――
第三章 建安文質論考――阮瑀・応瑒の「文質論」とその周辺――
第四章 王弼形而上学再考
第五章 言尽意・言不尽意論考
第六章 言外の恍惚の前に――阮籍の三玄論――
第七章 言語と沈黙を超えて――王坦之「廃荘論」考――
第八章 形而上への突破――孫綽小考――
第九章 逍遥の彼方へ――支遁形而上学考――
第十章 辞人の位置――沈約『宋書』謝霊運伝論考――
第十一章 経典の枝條――『文心雕龍』の立文思想――
第十二章 隠――『文心雕龍』の言語思想――
参考文献一覧
あとがき
内容説明
【本書より】(抜粋)
本書は、中国六朝時代の思想史の一側面を照射しようとするものであり、『六朝言語思想史研究』と題する。本書の射程を示す「六朝」の語は、厳密には建康に建都した六王朝――三国呉、東晋、劉宋、南斉、梁、陳を指すのであるが、本書では研究史の通例にしたがい、「六朝」の語を「魏晋南北朝」とほぼ同義のものとして用いる。すなわち秦漢/隋唐という帝国統一時代のあいだに位置する、三国鼎立から魏晋交替期、漢人国家の南渡と五胡十六国、そして南北朝分立時代を含む約四百年間におよぶ動乱期の全体を、本書では「六朝時代」と呼ぶことにする。……本書では、六朝時代にあっては儒教が衰退したために他思想が前景化したのではなく、むしろ六朝時代の儒教が道仏あるいは老荘、文学といった文化的諸価値を積極的に含み込みながら、それらの複合体であり、かつ有機的な運動体として不定形に展開した、という思想史的仮説を提起する。そしてその実相について、本書では言語思想(合理的精神としての「言語」/形而上的至高としての「言語を超えるもの」)を基軸に据えて検討し、またとくに「文(文章)」が必ずしも近代的「文学」概念に一致するものではなく、国家の基幹を決定する正統性に関わるものであることを検証することで、諸文化の基層的部分にある儒教的エートスの究明を目指すことにする。これにより、複雑に展開する六朝思想史を新たなパラダイムのもとに一貫したものとして提示することが可能となる、とみる。
【内容目次・概要】
序 論
第一章 大道の中――徐幹『中論』の思想史的位置――
徐幹『中論』は伝統的儒家思想に立脚しつつも、儒教の理想を『周易』の「窮理」に依拠しながら形而上的境位に求めていた。本書では、儒教の古典的正統性や規範・教化の淵源である「大道の中(大道之中)」[『中論』覈辯篇]の語に着目し、彼の行論が魏晋玄学の先駆をなす一面を有していたことを論じる。
第二章 経国の大業――曹丕文章経国論考――
国魏文帝・曹丕による文章経国論について、彼が「一家の言を成す(成一家言)」[『典論』論文]と称揚した徐幹『中論』の議論を参照しつつ、その内実を探求する。またあわせて、曹丕による文章の制作が彼自身による「一家の言(一家言)」を構想するものであったことについても論及。
第三章 建安文質論考――阮瑀・応瑒の「文質論」とその周辺――
建安期の「文質論」とその背後にある思想的堆積について検証する。またとくに応瑒「文質論」をめぐって、彼が従来の文質説に対してことさらに「文」を重要視していたことの思想史的意義を検討する。
第四章 王弼形而上学再考
三国魏・王弼の形而上学的思索をめぐって、「道」と「無」を同一視する主流的見解に対し、近年のヨーロッパにおける解釈をふまえつつ再考する。そしてとくに概念的把握(称)という観点から「道」と「無」とが同一ではないことを論証する。
第五章 言尽意・言不尽意論考
魏晋玄学における言尽意・言不尽意問題について、何晏(言不尽意)、欧陽建(言尽意)の議論を検討する。また王弼が語ること(言語)と示すこと(卦象)という二重の方法により「尽意」を模索していたことについて、『周易略例』明象篇を中心に考察する。
第六章 言外の恍惚の前に――阮籍の三玄論――
阮籍による老荘易三玄の解釈を検討する。阮籍は『老子』『荘子』『周易』の三玄すべてについて「論」を著すことで形而上的至高の理知的把捉を試みたが、彼の思弁的構想は、その究極的至高の手前において途絶していた。本書では、かかる途絶こそが、言語を超絶した彼の内的経験の純粋性・絶対性を保証するものであったことを論じる。
第七章 言語と沈黙を超えて――王坦之「廃荘論」考――
東晋・王坦之「廃荘論」を考察の対象とする。彼は当時の放達的気運の思想的元凶を『荘子』に求め、儒教唱導の立場から「廃荘論」を著したのであるが、その行論は、批判の対象である『荘子』を含めた老荘易三玄に依拠するものであり、また王弼、郭象など、魏晋玄学の影響が濃厚であった。本書ではさらに、王坦之が当時の仏教的思惟の影響下にありながら、言語/沈黙の相対的対立を超える地平を開示しようとしていたことを究明する。
第八章 形而上への突破――孫綽小考――
東晋・孫綽が老荘的「道」を紐帯としつつ、儒仏道三教を融和的に統合していたことを論じる。さらに孫綽「遊天台山賦」にもとづき、彼が魏晋玄学や仏教的思惟を踏襲しながら、実際に形而上的境位への突破を志向していたことを検証する。
第九章 逍遥の彼方へ――支遁形而上学考――
東晋の沙門・支遁の『荘子』逍遥遊解釈と般若思想解釈とをとりあげ、彼が般若思想を媒介として魏晋玄学の形而上学的思惟にさらなる展開をもたらしたことを論じる。支遁は万物の基底的実在のさらなる深奥を模索し、その体認を企図していたが、かかる基底中の基底について、本書では思弁的追跡とその忘却とに着目して検討する。
第十章 辞人の位置――沈約『宋書』謝霊運伝論考――
『宋書』謝霊運伝論における「辞人」の評価に着目し、沈約があらゆる「文章」を儒教の古典的正統性の内部に位置づけようとしていたことを論ずる。そしてそのための理論的根拠として、彼が音律の数理的整合性を律暦思想(数理科学)に裏付けられてきたことに論及する。
第十一章 経典の枝條――『文心雕龍』の立文思想――
劉勰『文心雕龍』を考察の対象とする。とくに「経典の枝條(経典枝條)」[『文心雕龍』序志篇]の語に着目し、彼があらゆる「文章」を経典的価値のもとに集束させ、国家秩序の確立のための資源とみていたことを論じ、またあわせて彼の経書観、文章観にもとづく立文思想を探求する。
第十二章 隠――『文心雕龍』の言語思想――
劉勰『文心雕龍』における「隠」という概念について、従来指摘されてきたような単なる修辞上の余韻、含蓄というものではなく、劉勰が『周易』の「互体」という卦爻操作に依拠しながら、言外の境位を言語以外の知的構造において把捉する可能性をみていたことを論じる。
A Study of the Philosophy of Language in the Six Dynasties Period