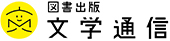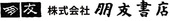目次
第一部 古代都城制から中世都市へ
第一章 東アジア世界の中の都市平泉
第一節 日中都城制比較の視点
第二節 中国都城の街路
一 街路管理システム
二 街路の管理体制 1街路の維持制度 2侵 街 3種 植
三 中国都城の街路
第三節 日本の条坊制
第二章 東アジアにおける都市造営と平泉の比較研究
第一節 隋唐長安城の特異性
一 唐長安城と隋大興城 二 隋以前の都城 三 隋唐長安城の特徴 四 唐の坊牆制
第二節 日本の坊と坊門
一 日本都城の坊 二 坊令と坊長 三 坊門と坊令
第三節 坊門の開閉とカギ 一 坊門の開閉 二 坊門のカギ
第四節 中世都市への展望
第三章 漏刻と時報・諸門開閉システム
第一節 鐘楼・鼓楼の設置
一 鐘楼・鼓楼の設置場所と機能 二 鼓楼・鐘楼の設置と時報
第二節 時報と開閉門鼓
一 開閉門システム 二 承天門と漏刻 三 日本の宮都と時報
第四章 平泉の特殊性
第一節 都城イメージの変容
一 『将門記』の中の都イメージ 二 輪田(福原)遷都に見る都イメージ
第二節 国府と地方有力者の家
一 国府の様相
二 本拠地の様子 1平泉にいたるまで 2鎌倉の画期性 3平泉の再検討
第五章 中国の地方都市と平泉
第一節 中国の地方都市
一 日中の地方都市比較の可能性 二 草市・鎮市の概要 三 鎮市の形
第二節 日本の都市と平泉
一 宮都と国府 二 日本の地方小都市 三 武士の居館 四 都市類型と平泉
第二部 平泉と武士居館
第一章 国庁と国司館
第一節 国司館の内部 第二節 国庁と国司館の関係 第三節 国司館へ
第二章 中世城館の成立
第一節 中世城館論の展開 第二節 平安時代の武士の家 第三節 奥州藤原氏の場合
第三章 白河・鳥羽・平泉
第一節 白河・鳥羽 一 白 河 二 鳥 羽
第二節 平 泉 一 大内城跡 二 上浜田遺跡 三 家作制限令
第四章 武士の館の構造――侍所について――
第一節 貴族住宅の侍所の構造
第二節 鎌倉幕府の侍所 一 将軍御所の概要 二 侍所の構造 三 侍所の機能
第三節 御家人邸の侍所 第四節 幕府的侍所の成立
第五章 宴の空間
第一節 室町幕府の宴
一 室町将軍御所の宴の空間 二 室町将軍の宴の空間――他の邸宅における宴――
第二節 正月儀礼の展開――鎌倉幕府から室町幕府へ――
第三節 内郭構造の変質
成稿一覧/あとがき/英文要旨/索 引
内容説明
【本書より】(抜粋)
本書は、平安時代後期に奥州藤原氏が拠点を置いていた平泉について、古代以降の都市の歴史的展開の中で捉えようと試みたものである。日本の古代国家が中国から都城制を導入して都造りを始め、それがどのように平泉へと繋がっていくのか、そうした問題に取り組んだ拙文を集成している。(あとがき より)
平泉、そしてそこに本拠を置いていた奥州藤原氏に関わる研究は、これまでに重厚な蓄積がある。古くは近世の地誌類に始まり、近年の東アジア世界との交流を視野に入れた研究まで、幅広く研究が進められている。そうした長い研究史の中で、大きく二つの画期があったように思われる。一つは、戦後まもなく始まった寺院跡の発掘調査と中尊寺金色堂内の御遺体調査、ならびに金色堂の保存修理工事である。二つ目の画期は、一九八〇年代末から始まった柳之御所遺跡の発掘調査であった。第一の画期が寺院を中心とした調査であったのに対して、柳之御所遺跡は、政治的な場であり世俗的な場と考えられる遺跡であった。そうした遺跡にメスが入れられたのである。これによって奥州藤原氏の実像に迫る成果が上がり、直接的には今日に至る研究の流れを形作ることとなったのである。
戦後の寺院を中心とした研究からは、京都の文化に劣らないものを平泉にも導入し実現していたことが明らかになるとともに、そうした側面が強調されてきた。それに対し第二の画期となった柳之御所遺跡の発掘調査では、奥州藤原氏の政治的・経済的な側面が具体的な遺物や遺構として立ち現れ、平泉の都市的様相がうかがえるようになってきたのである。そうした経緯の中で、中世都市として平泉が評価されるとともに、日本の都市史、あるいは東アジアの都市史の中で、どのように平泉を理解することができるのか、という問題が生まれてきた。平泉研究に着手した当初から常に念頭に置いていたことは、平泉や奥州藤原氏をあまり特別視しないように心懸けるということである。つまり、古代以来、服従を強いられながらも、奥州藤原氏は平泉に独自の政権を築き、京都の貴族文化に劣らない高い文化を花開かせていた。蝦夷の系譜に連なる独自性を強調しつつも、中央の文化への強い憧れが反面に存在するというパラドクシカルな一面が潜んでいるように思われる。もちろん、先学が明らかにしてきたように、奥州藤原氏という存在は特異であり、その拠点である平泉も特殊な性格を持っている。しかし、そうした特殊な面だけを強調せず、日本列島全体、あるいは東アジアの中で考え直してみたいという思いを持ってきた。本書は、そうしたことを意識しながら、牛の如き歩みで進んできた軌跡である。(序 より)