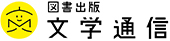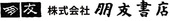目次
中国古代の学と校 ……………………………………………………………………………………… 小南一郎
漢代経学の相貌――宇宙論的「知」の形成 ………………………………………………………… 辛 賢
六朝時代における家学とその周辺 …………………………………………………………………… 吉川忠夫
梁代の仏教――学術としての二三の特徴 …………………………………………………………… 船山 徹
宋代における経学と政治――王安石と朱熹の異同 ………………………………………………… 小島 毅
中国近世の書院と宋明理学――「講学」という学問のかたち …………………………………… 鶴成久章
モンゴル王族と漢児キタイの技術主義集団 ………………………………………………………… 宮 紀子
人法兼任の微意――明代中後期の科挙および督学制度と思想史 ………………………………… 三浦秀一
清代学術と幕府――編纂と代作の状況を中心として ……………………………………………… 水上雅晴
「仁義礼智」を捨てよう――中央研究院歴史語言研究所の出現 ………………………………… 平田昌司
あとがき/執筆者紹介
内容説明
思想史が、それぞれの時代を代表する思想家たちが築き上げて来た思想の体系を解説し、それを分析することを中心にして記述されるのは当然のことであろう。各時代に固有な思想的な課題が、個々の思想家たちの思索を通して、結晶化され、その解答が提示されているのである。思想家たちが、苦悩を通して築き上げて来た思想の体系は、歴史の流れの中でその内容が検討され、改変が加えられつつ、時代を越えて継承されて来た。一人の思想家が思索を行なうのは、前代から受け継いだ思想的な遺産の基礎の上に立つだけではなく、その時代に固有な社会的環境の中においてであった。たとえ孤高の思想家がいたとしても、孤高という姿勢を取ること自体が、そうした態度を通して、固有の社会と関わりあっていたのである。
この論文集は、中国の思想家たちが思索を行なって得た、その精華を論ずるよりも、思索を行なう際の基礎条件の方に目を注ぎ、そうした条件が、時代の流れの中でどのように変化し、それが個々の時代の思想の具体的なあり方にどのように関わりあっていたのかを考えようとするものである。思想的営為をその基礎で支えて来た文化的要件には、多様な性格のものが存在していたであろう。精神文化的要素の占める割りあいの大きいものもあれば、社会制度的なものもあった。ここでは、特に思想の場を取り挙げて、検討を加えてみたいと思う。言うまでもなく、思想家たちの思索は架空の場でなされるわけではない。それぞれの社会に特徴的な思索のための場があり、またその成果を公表し、伝承するためにも固有の場や形式があったのである。
そうした場や形式を離れて、思索はあり得なかった。思想的営為の背後にあったそうした要件を把握することによって、思想史の記述を、より人間的な、血の通ったものとすることができるはずなのである。
この論文集では、問題をさらにしぼり、知の伝承・伝播の問題を中心に据えて、その知の継承の具体的な場であり、制度的な枠組みでもある学問のあり方を見てみようとした。それぞれの時代の教育・学習の具体的なかたちが、その時代の思想のあり方にさまざまな影響を及ぼしていたに違いないが、その相関の様子を考えるための前提として、学問の場という基礎的部分に目を注ぎ、それぞれの時代に特徴的な様相を検討しようとしたのである。
小南一郎「中国古代の学と校」は、中国における学校制度の形成について、新石器時代から秦漢時期までを概観したものである。礼関係の文献の中から、部族社会にまでさかのぼるであろう教育の様相を伝える資料を探して、そこに記された郷村の教育制度の中に、中国の学問の原型となるものがあり、おそらく戦国時代ごろまで、そうした古い要素が、大きく変貌することなく、伝えられていただろうことを論じた。
辛賢氏の「漢代経学の相貌――宇宙論的「知」の形成」の論文は、漢代の人々の思考のかたちを、より基礎的な部分で見ようとしたものである。特に漢代の易学が、象数易と呼ばれる占卜的要素の強いものであったことの意味を追及している。漢代の易には、 現実的な事象の吉凶を占うという性格が強く留められていた。こうした漢代の易学の背後に、この時代の人々に特徴的な〈天〉と〈人〉とを結ぶ観念があったと辛氏は指摘する。
吉川忠夫氏「六朝時代における家学とその周辺」の論文は、この時代に特徴的な学問のありかたについて、家学という視点から検討を加えている。六朝時期になると、門閥貴族体制の文化的な優位を反映して、一つの家系の中で学問を継承する、「家学」と呼ばれる学問のあり方が顕著になる。まず順陽の范氏が継承した家学の内容を検討し、范寧の「春秋穀梁伝集解」という注釈書が、范氏一族の人々、およびその周辺にいた門生故吏たちの共同作業として作り上げられたことを確認する。加えて、この時期の学問の伝承は、漢代の師法の継承を中心とする学問に比べて、より開かれたものであり、范氏の家学の伝統は、「理」を追及する中から、仏教信仰などにも繋がるものであったことを指摘する。
船山徹氏「梁代の仏教――学術としての二三の特徴」の論文は、仏教史の流れの中で、梁代という時代が具えていた特徴的な性格について分析を加えている。インドに原典のある仏教経典の漢訳作業は、五胡十六国時代、後秦の鳩摩羅什あたりが頂点となり、梁代になれば、さらに下った時期に中国に伝来して流行することになる唯識思想の論書と密教経典とを除き、主要な経典の漢訳はほぼ終わっていた。仏教活動の中心が、訳経から、訳された経典の整理と咀嚼、理解へと移っていたのである。こうした学問的仏教の進展と対応して、梁代ころになると、もっぱら仏教関係書を収蔵する図書館を指す言葉として、経蔵・経台・般若台などの語が用いられるようになると、船山氏は指摘する。
小島毅氏「宋代における経学と政治――王安石と朱熹」の論文は、大きくいえば宋代の学問として一括できるが、方向性に違いが見える、王安石と朱熹との二人の学問のありかたを、両者の経書注釈を通して検討したものである。これまで、王安石の学問は経学、朱熹の学問は道学と呼んで区別をされることが多かった。しかし、小島氏は、まず、両者の学問が基本部分で共通していたことを確認する。王安石の経典解釈は、天子を輔弼する宰相としての立場を基本としたものであり、朱熹の解釈は、支配者を善導することをめざして意見を述べる士大夫の立場を基本とするものであって、王安石と朱熹との経典解釈の違いは、両者の政治世界での立場の違いを反映するものであったと、小島氏は理解する。
鶴成久章氏「近世中国の書院と宋明理学――「講学」という学問のかたち」の論文は、書院の具える様々な機能(蔵書のための施設という性格など)の中でも、特に重要なのは「講学」活動であったとして、その内容を詳しく分析している。
宮紀子氏「モンゴル王族と漢児の技術主義集団」の論文は、知の空間的(地域的)な伝播の問題に注目している。しかもその知は、儒家の経典に由来するものではなく、主として自然科学的なものであった。医学などに代表されるように、直接的な有用性を具えた、技術的な知識なのである。そうした技術的知識を持つ人々を、モンゴルの王族たちは、争うようにして自分の手元に置こうとした。この時代に勢力を伸ばした新しい道教、全真教の教祖たちも、こうした技術的知識に深く関わっていたと宮氏は指摘している。
三浦秀一氏「人法兼任の微意――明代中後期の科挙および督学制度と思想史」の論文は、従前の見方に訂正をせまるものである。三浦氏は、明代の科挙をめぐる制度的な問題や具体的な科挙試験問題の模範解答(程文)を検討して、そこに明代の思想家たちに課せられた問題が反映していることを確認する。とりわけ、試験の実務にあたる督学官たちの、思想的な立場からの使命感と職務の実態との乖離に由来する苦悩を分析し、そうした苦悩とその克服との中に明代の思想の具体的なありかたを見ようとしている。
水上雅晴氏「清代学術と幕府――編纂と代作の状況を中心として」の論文は、当時の有力者たちが開いた幕府に幕友としてそれに関わった学者たちの実態を詳しく分析している。幕府の府主が学者たちを自分のもとに集めたのは、そこでの学術活動の中心が書物の編纂にあったからである。幕府で行なわれた編纂作業の中心は、地方志の編纂、失われた書物の復元(輯逸)、古典のテキストの校勘などにあり、府主の政治的立場は資料の収集を容易にし、集まった幕友たちの共同作業が、学術研究の基礎資料となるような書物を次々と生み出した。
平田昌司氏「「仁義礼智」を捨てよう――中央研究院歴史語言研究所の出現」の論文は、思想的課題に中国の人々がどのように対応したのかを、歴史的な動きの中で、詳しく分析している。西洋の学術思想と中国の伝統的な思想とのもっとも大きな違いは、西洋の学術が自然科学を基礎に置き、そこで探求される真理は善悪の観念に関わらないとされるのに対して、中国の学問は基本的に人間的・社会的な善(倫理)を求めてなされるものであったことにあるだろう。もちろん中国にも自然科学的な学問の伝統もあったが、学問の主流は人文学にあり、そこでの探求の方向は、倫理的価値観と切り離せないものであった。西洋の自然科学の持つ体系性や論理性に引かれて、二十世紀の初頭のころ、自然科学の教育を受けた、著名な知識人は少なくない。ただ、かれらの多くが、やがて自然科学の学問から離れてしまう。中国の「国粋」尊重へもどってしまう者たちもいた。そうした中で、自然科学的客観性を保持しながらも、中国の文化伝統へ目を注ぐべく、民衆的文化を対象とする学問が築かれた(平田氏は、こうした流れを〈土の声を聴く〉と表現している)。中国の古典も、さかのぼってゆけば〈土の声〉に由来すると考えるのである。
研究者は、学問という回路を介して社会とつながっている。その学問は、それぞれの時代に固有な、特殊なかたちの学問なのである。研究は「実事求是」をスローガンとするとはいえ、「事」の主体をどこに置くか、求められる「是」の内容について、どのような点を重視するのかなどについては、時代の価値観が色濃く反映することになる。我々の学問も、現在という時代の中に囚われた学問であるのかも知れない。そのようにみずからの学問を客観視することは、むしろ必要なことであるだろう。しかし一方で、学問の歴史を詳しく見るとき、時代的な制約の下に縮こまるだけでなく、それを乗り越えようとする人間の精神の羽ばたきをも、そこに感じ取ることができるように思うのである。