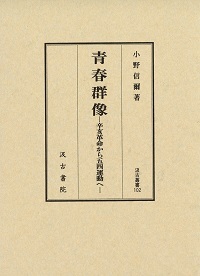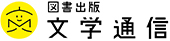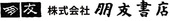内容説明
「五四運動は、日本や欧米列強に対する反帝国主義運動であったばかりでなく、辛亥革命に遅れてきた思想革命でもあった」とする著者が、革命の渦中を生き抜いた青年たちを通して中国近代史の実相に迫る。
【本書より】(抜粋)
私の近代中国史研究は、清末農民戦争からはじまったが、当時、京都大学人文科学研究所の桑原武夫氏の主宰する「ブルジョワ革命の比較研究」に参加する機会を得て、近代中国を多角的に照射することの必要性を学ぶとともに、ヨーロッパとは単純に比較できない半植民地中国の特異性をも強く意識することになった。中国のブルジョワ革命をどこにおくかについては種々議論があろうが、さしあたり孫文の辛亥革命におくのが穏当であろう。あたかも中国では一九五〇年代後半から、辛亥革命に関する基礎資料や回想録の類が出版されるようになり、中国同盟会の機関誌『民報』(全四冊)も復刻されて、辛亥革命研究のための条件が整いつつあった。・・・ 私はそのなかでも、革命思想がどのように宣伝され、若い青年たちを組織したかに関心をもった。鄒容は『革命軍』を書いた時、わずかに十八歳、陳天華が『警世鐘』を書いたのは二十八歳、いずれも年若い青年たちであった。島田虔次先生との共編『辛亥革命の思想』や、本書の第一章辛亥革命と革命宣伝は、これら青年たちの宣伝パンフレットを翻訳し、中国近代の革命思想とはいかなるものであるかを一般の読者に紹介しようとしたものであった。この際、私はそれまで軽視されがちであった回想録の類を渉猟して、革命の主体が何を宣伝しようとしたか、そしてその内容が被宣伝者の知識と関心によって規定されたか、そのプロセスを具体的に明らかにしようとした。その結果、宣伝の重点は反満民族主義におかれ、西欧のブルジョア革命とはその綱領や革命宣伝においてかなり様相を異にしていることを知った。私は毛沢東が「五四運動時期にはまだ中国共産党はなかったけれどもすでにロシア革命に賛成し初歩的な共産主義思想をもつ相当数の知識分子がいた」(新民主主義論)と述べていることにこだわってきたが、これは毛沢東だから許容された発言であって、護教論的マルクス=レーニン主義の観点からすれば、とんでもない発言であった。しかしこれは彼自身の正直な実感であったはずである。毛沢東が自らをその一人に数えているとすれば、羅家倫も当然そのなかにふくまれてよい。このような思想状況のなかでロシア革命と第一次世界大戦は中国人に社会主義という出路を示した。毛沢東によれば「ロシア式の革命は、私から見れば、如何ともなしがたい、到底通り抜けられない道ゆえの選択であって、もっといい方法があるのにそれを放棄したわけでは決してなく、ただこんな暴力的な方法をとらなければならなかっただけである」(在フランスの新民学会の友人たちへの手紙 一九二〇)という。こうした歴史的条件のなかで、青年たちのなかからマルクス=レーニン主義を選択し、中国共産党に参加する者が現れたが、それと同時に彼らの間に思想的分化が起こったのも必然であった。 この分化がどのようにして起こったか、つまり「分道揚鑣」の素因がいったい何であり、何を契機としていたか、を実証的に腑分けし、歴史の大きな転換をその基底の位相において解明しようとして書いたのが、五四時期の青年たちに関する論文であった。先の辛亥革命において革命宣伝を担った青年たちと併せ、「青春群像―辛亥革命から五四運動へ―」と書名に冠した所以である。また本書には、彼らをこのように急進化させていく一要因となった日本帝国主義の当時の大陸侵略工作についての若干の論文をも収めた。